PR: 966戸の間取りから、空住戸を検索!
【その3】念 系統別①(操・放・特)【念関連2】
【その2】念の威力・精度ほか【念関連2】 の続き。
<もくじ>
◆操作系
┣操作系能力への抵抗可能性
┣無主物先占の法理
┗念のコンボについて
◆放出系
◆特質系
◆操作系
→物体や生物を操ったり、ルールの創出とその強制ができる系統。
操作系能力は生物や物体を媒介しないとその力を発揮できない上、特に物体操作の場合は使いこんだモノ(愛着のあるもの)でないと威力・精度が上昇しないことが多い。
さて、そうして本題に入りたいのだが、上記定義の前段「物体や生物を操る」は、どうも後段の「ルールの創出とその強制・付加」に集約されるように思われるため、それを重点的に考えたい。
作中から大きく2つの性質を挙げる。
①他人の創ったルールには干渉できない("除念"除く)
②絶対的ルールは創れない
①他人の創ったルールには干渉できない("除念"を除く)
誤解を恐れず端的に言えば、"除念という例外を除いて―「ルールは壊せない」"という意味だ。
この大前提がなければ「ルールを強いる」の操作系能力の意味がなく、相手はルールに則ってあるいはルールに反しない範囲で行動し、攻略しなければならない。
(※当然負ける事になるが、必ずしもルールに従う必要性はない。)
②絶対的ルールは創れない

具現化系能力者が『神懸ったもの=人間の力を超えるもの=絶対的なもの』を具現できないのだから、
操作系能力者も『絶対的ルール』を相手に強いる事はできない、というのは至極自然な発想であろう。
『絶対的ルール』は創れないを言い換えれば、
能力者が『絶対的に勝てるルール』を相手に強いる事ができない、
もっと砕けて言えば、『(相手にとって)無理ゲー』は創れない、ということ。
補足をするならば、この『絶対的』の意味は、『主観的な絶対性』ではなく、『客観的な絶対性』を指す。
例えば―
私がゲンスルーの『命の音(カウントダウン)』を仕掛けられ、発動した場合。
(解除方法は、『時間制限内にゲンスルーの体に触れながら"ボマー捕まえた"と告げること』)
客観的には、その解除方法は達成不可能ではないが、
主観的には、どう考えても私が実現する事は不可能である。
私から見てどう考えても『無理ゲー』だから、こんな能力はおかしい!
と言いたいところだが、それは単純に私が弱いという事に過ぎない。
◇操作系能力・簡易まとめ
①ルールは壊せない
②絶対的ルールは創れない
◇操作系能力への抵抗可能性
操作系能力の中には、物体操作と呼ばれるような「それ自体の操作」を目的とするものがある。
その中で、特に高度な精神構造を持つ生物(人間等)への操作能力について。
Q:一度"操作"されてしまった場合、その操作に抗う事はできないのか。
A:基本的にできないが、例外的にできうるのかも。
"操作"は、大きく部分(条件)操作と完全操作に分けられそうな感じはするが、部分(条件)操作の場合にはその前例らしきものがある。
つまりはキルアとジャイロである。
ちなみに部分(条件)操作とは、一切自由に動けないのではなく、ある条件下において行動を制限させる操作、あるいは体のある一部分だけの操作のことを指している。
キルアは、脳に刺された針によって、ある状況下である行動を取るように(取らないように)強制されて(仕向けられて)いた。
つまり部分(条件)操作状態にあったのだろうが、自ら針を抜きその操作状態から自力で抜けだした。
ジャイロの場合。
明確に女王による念操作があったとは言われていないが、原生生物に比べ多用な個をもつ人間キメラアント、それも前世の記憶を有している者達が女王の下から離れようせず、「完全に」ではないが、ある一定の行為をしないように、またするように強制されて(仕向けられて)いたように思われる。
そんな蟻達が、女王絶命後(王誕生後)、手の平を返すが如く態度を変えた。
これは、女王誕生前と後で階級の分裂が起きるというキメラアントの生態通りなのだが、原生生物ならばまだしも、人としての記憶を持つ者達がそう易々とそのロールプレイに従う事には疑問があった。
女王が、意識的にそれを用いているのかはわからないが、対等関係にある王以外の子にはそのような操作プログラムが組まれていたのではないかと思っている。
そして、そんな蟻の中にあって、女王存命中にそこから離れた者がいた。
これは神の声(ナレーション)が附されていたが、どうも強靭なる精神力によるもののようである。
以上の事から少なくとも部分(条件)操作は―その能力の性質や、縛った行動の幅にもよるのだろうが―尋常ならざる精神力でもって抗う事ができうるのかもしれない。
対して、完全操作の場合。
・イルミの『針(能力名不明)』
・シャルナークの『携帯する他人の運命(ブラックボイス)』
などが挙げられうるだろうか。
―で問題は、これに抗う事ができるのか、という事。
かみ砕いてしまえば、オーラの量も質も精神力もさほど強くない低位の操作系能力者の『完全操作』に、王やネテロが屈することがあるのか、ということだ。
もちろん、"操作系能力の性質上一定の駆け引きを前提とするわけで、稚拙な能力者がそんなのできるわけない"だとか、確証も何もないが"完全操作は高位の能力で低位の能力者には使えない"、なんていう反論は有効だろうが、"能力も使え"て、"駆け引きにも勝った"という前提で考える。
恐らく負けるだろう。
実際、攻防力の問題でシャルナークのアンテナが王に刺さるハズもないでしょうけど、操作系能力のそれぞれがハメたら勝ちなわけで、相手が条件を破った場合は「命」すらも奪うことができてしまう。
そして、これまで「完全操作」があるのかどうかわかりかねていたんですが、そもそも相手に「命」すらも手の内にあるのだから、あってもおかしくはないんでしょうね。
まぁ、傍からは完全操作に見えるだけで、本当は縛りの強い部分(条件)操作なのかもしれないんですけどね。
印象の方向性が決まったところで、それに沿って考えてみる。
さきほどは―
部分(条件)操作だから、尋常ならざる精神力で覆し得る
完全操作だから、尋常ならざる精神力でもっても覆し得ない
―と考えてみたのだがそうではなくて、キルアやジャイロのケースは"縛りの弱い"部分(条件)操作だったから、精神力で覆せたのではなかろうか。
若干念から離れて考えてみるが、どうも"縛りの弱い"部分(条件)操作は監禁+強迫(脅迫)に近しい気がする。
相手に何かを強制させようと、手足を紐やら手錠で縛って"●●をやれ"と言ってるようなイメージだ。
そして、監禁されてる者はその多くが中々逃げられないだろうが、尋常ならざる行動力・精神力があれば拘束から逃れられるかもしれない。
対して、"縛りの強い"部分(条件)操作or完全操作は、監禁+お薬注射に近しい気がする。
あんまりこうゆうことを書いてると危ない人になってしまうのでそこまで言及しないが、その薬によって精神を半壊or全壊されてしまえば、もはや逃げることはかなわないだろう。
これをまた念の世界に戻す。
キルアやジャイロが操作から抜けだしたことは、操作系能力のルール①ルールは壊せないに反しているのではなく、尋常ならざる精神力を以って覆されるのが"縛りの弱い"部分(条件)操作故の受動的制約からではなかろうか。
<"縛りの弱い"部分(条件)操作>(半自由人形)
・一定の条件下では行動を縛られるが、それ以外では自由があり意思もある
・行動全てをプログラムする必要はなく、その者の意思や判断を基盤にできる
<"縛りの強い"部分(条件)操作or完全操作>(不自由人形)
・全ての行動を縛られ(?)、一切の自由がなく意思もない(心神耗弱or喪失状態)
・行動全てをプログラム化する必要がある上、木偶化
まず、念での戦いにおいて敵の能力がわからないのが普通であるからして、"人形"の行動全てをプログラム化するのは非常に難しい。
そのため―"人形"自体が念を理解し対応できることが前提ではあるが―"人形"の意思を残しそれを基盤に一定条件下でプログロムを作動させた方が、ともすれば"人形"としての精度は高い。
つまり、精度上昇というメリットを得るために相手(人形)に尋常ならざる精神力で逃げられるというリスクを払っている、という能動的制約とも採れるかもしれないし、
相手(人形)に意志を残すこと自体が―監禁した相手に逃げられてしまうように―反射としての受動的制約とも採れるのかもしれない。
個人的な緩いイメージでは―
縛りの緩い部分(条件)操作…「have to」型操作=尋常ならざる精神力で以って抵抗可能
縛りの強い部分(条件)操作(=完全操作?)…「must」型操作=自力では抵抗不可
―こんな感じかもしれない。
◇生物操作の絶対性・簡易まとめ
基本的には抵抗不可能なのだろう。
しかし、能動的or受動的制約等を理由に、尋常ならざる精神力で抵抗が可能なものもあるのかもしれない。
◇無主物先占の法理

主人となる能力者がいない、物(人含む)は操作できるが、すでに主人となる能力者が居た場合は操作できない。
つまり早い者勝ち。
この性質を利用して、「部分(条件)操作」や「完全操作」を"簡単に"防げないのだろうか。
―例えば、自身に以下の操作プログラムを与える。
◇『牙を抜かれし者(ベン・ザ・ダウン)』
(「部分(条件)操作」「対自分(男)」)
トイレで用(小)を足し、トイレから出る際に必ず便座を下げさせる能力。
トイレから出る時かつ、便座を上げてから「下げる」行為をしていない場合、発動する。
このように、自分の人格や戦闘を害しない程度の操作を最初から自分に加えていた場合、どうなのだろう。
つまり、操作系能力全てがバッティングするのか。しないものがあるのか否か。
「完全操作」>「部分(条件)操作」で、かつ性質が同じ場合にバッティングが起こるのだろうか。
具体的に考えるならば、
対象者の右手を自由に操る能力者Aと
対象者の左手を自由に操る能力者Bが居たとして、2人は同時にXの手を操作できるのか。
右手と左手、操作部分が被っていないから、バッティングせず操作できるのかもしれない。
しかしながら、ひょっとすると部分(条件)操作にしろ完全操作にしろ、相手を操る事は『対象者の脳を操作する』事と言えるのかもしれない。
そうすると、このAにしろ、Bにしろ、対象者の脳のうち運動中枢を操作する事で、対象者の手を操作しているのであれば、バッティングし操作できないのかもしれない。
では少し毛色を変えて、内部プログラムから操る能力(内圧的操作)と、外部プログラムから操る能力(外圧的操作)が競合した場合、どうなるのか。
作中の描写や根拠に欠けるため判断が難しいところではあるのだが、内圧的操作(ex.イルミの針操作)と、外圧的操作(ex.ピトーの操り人形)は競合せず、同時操作が成立しそうな印象は受ける。
(命令がバッティングして人形はろくに動けないだろうが、念能力としては同時に成立するかも、ということ)
そして、さきほどの「ベン・ザ・ザウン」などの「自己操作で対抗できうるか」だが、恐らく対抗できない。
それで対抗できてしまったら操作系能力者の意味がないだろ、という感覚的な印象が前提にあるのだが、
便座を下ろし忘れ「ベン・ザ・ダウン」が"発動"している、数秒の間に他の能力者が能力を使用した場合、無主物先占の法理により、操作は失敗だろう。
(例えば、ベン・ザ・ダウン発動中にシャルナークが私にアンテナを刺した場合、便座を下ろし終わるまで数秒間は発動しないが、下ろし終わった瞬間発動すると思われる)
しかし、「ベン・ザ・ダウン」が発動していない"潜在化"状態に、他の能力者が能力を使用した場合は、競合は起きず操作は成立すると思われる。
つまり、発動状況を常に維持できる操作プログラムならば、無主物先占の法理で他能力者による操作を防げるだろうが、非常にコスパが悪いか、逆に弱くなるケースの方が多そうである。
◇無主物先占の法理・簡易まとめ
操作系能力その全てが無主物先占の法理で弾かれる、ということではないのかもしれない(ex.内圧操作VS外圧操作)。
◇念のコンボについて
「絶対的ルールは創れない」に関連した話。
念と念はコンボしうる(=できないものもある)。
東ゴルドー城突入直後のユピーへのハコワレ発動の際に、
"『神の共犯者』と『ハコワレ』の連携(コンボ)が可能であることは無論事前に検証を終えている"
というナレーション(神の声)が附されていた。
どんな念と念でもコンボが可能ならば―「事前に検証」をする必要性がない。
つまり、
コンボが成立しない(発動しない)
能力の変容が起きる
など、コンボ不成立の可能性があるという事だ。
そして、コンボ不成立の1つの要因として、コンボによる絶対性の成立が挙げられよう。
Q:.メレオロンの『神の共犯者』とノヴの『窓を開く者(スクリーム)』はコンボが可能か
『スクリーム』は作中で一度しか使われなかった技なので、詳細は不明。
「空間を開き相手の一部を取り込んだうえで空間を閉じる」ということからドラゴンボールでの気円斬のように"何でも切れる"ような印象を受ける(空間の断裂には、恐らく体の硬さ等は関係がない)。
しかし、そもそもの問題として、
『何でも切れる刀』は具現不可能なのに、『何でも切れる空間(の断裂)』は具現可能(実現可能)なのだろうか。
①切る事が目的ではない空間系能力の副産物としての『空間の断裂』だから可能なのか、
②無条件に"何でも切れる刀"を具現化ができないだけで、"窓に触れている者(物)を削り取る"という限定条件が附されているため可能なのか
③1:空間開く、2:開いた空間を相手に取り込む(当てる)、3:2を維持した状態で閉じる、という3行程を踏む事で、客観的絶対性が否定されているのか、
④それとも、スクリームは何でも切れる技ではないのか。
などなど。
個人的には③で処理できそうな気がするが、ここに突っ込み始めると本題から逸れ過ぎてしまうので、とりあえず、スクリームが体の硬さ等は関係がなく、窓に触れた者(物)は何でも倒しうる技である、とする。
その前提の上での答えだが、「神の共犯者」とのコンボは成立しない。
スクリームは大きく
1:空間を開く
2:開いた空間に相手を取りこむ(あてる)
3:2を維持した状態で閉じる
という3行程を踏む必要があり、相手はそれを回避しうる。
しかしながら、相手に自らの存在を一切知覚させない『神の共犯者』とコンボが可能ならば―
相手は、スクリームの上記3行程を知覚する事なく無抵抗のまま受け死ぬ事となるのだから
―それは相手に不可能を強いるのと等しい=コンボによる絶対性の成立。
よって、『神の共犯者』と『窓を開く者(スクリーム)』はコンボ不可能である。
◇念のコンボについて・簡易まとめ
念のコンボには成立しえないものがありうる。
特に操作系能力の色合いが強く、相手に強いるルールが強ければ強いものほど、難しいと思われる。
(ルール2:絶対的ルールは創れない)
結果として、コンボ不成立(発動しない)、あるいは能力や制約と誓約の変容が起きうる。
◆放出系
→オーラを外在化(EOP化)できる系統
放出系の最も顕著な性質は"POPもしくはAOPとの切り離し"にあろう。
もし、放出系能力で使用するオーラもAOPに含まれると考えた場合、放出系の利点はまるでなくなってしまう。
例えば、
AOP10000オーラの放出系能力者Xが、その全てを込めて10000オーラの念弾を作ったとする。
放出系能力もAOPに含まれるという前提ならば、その念弾が"生きて"いる間、術者は絶状態になるのだろう。
相手に命中する、あるいは破壊されたならばまだいいのだろうが、弾かれた場合や、どこかに飛ばされた場合、どうなるのだろうか。
念弾が生きているから、術者は能力を解除しオーラを回収せねばならないだろう。
<回収イメージ図>
しかし、念弾が放出系能力者Xと逆方向だったり、念空間に飛ばされた場合など、回収よりも先に敵の攻撃が来ることは十分ありうる。
すると、放出系能力者にも関わらず、うかつにオーラを飛ばせない事態につながりうる。
つまり、「放出系能力はAOPと切り離されている」と考える必要があろう、という事だ。
作中の描写で言えば、ゴン「あいこ」の発想自体が、
「放出系オーラの外在化」を示していると言えよう。
しかし、切り離した結果として、放出系能力は掛け捨て型=回収ができないもののように思われる。
◆特質系
→他に系統に類をみない系統
"例外"の総合商社で、強・放・変・具・操、以外の念。
特質系の能力が可能たる所以自体が推測できないものも多く、逆に最も理解に易い系統。
そうゆうものなのだ、と納得する他ないからである。
個人的には―解釈の挟みようがないため―もっとも嫌いな系統である。
特質系だけで単独に働くのではなく、具現化物や、物(肉体含む)を介して作用している能力が多い様子。
術者の心をもっとも強く反映する系統、と言えるかもしれない。
以下、【その4】念 系統別②(具・変・強)【念関連2】 へ続く。
【その4】念 系統別②(具・変・強)【念関連2】
<もくじ>
◆具現化系
┣手から離れた具現化物
┣遠隔操作(リモート)⇔自動操作型(オート)
┗無敵の具現化物・ポットクリン
◆変化系
┣オーラの形状変化について
┗オーラ以外の形状変化について
◆強化系
◆具現化系
→オーラや肉体を元に物質化ができる系統
これまで物質化の元になる材料は「オーラ」だけかと思っていたのだが、

ツボネの大和撫子七変化(ライダーズハイ)によって、オーラの他に「肉体」も材料にできることが示された。
「そんなこともできるのか、へぇ~」
なんて思ったものだが、思えばこれは最初の水見式の時点で示されていたのかもしれない。
具現化系は水見式において「水に不純物が出現」する。
しかしながら、従来の「オーラを元に物質化をしている」という理解で順番に追うと、

こうなるのだろう。
しかし、なんか違わないか、と。
元々想像していた順番自体、これなのだ。
そして、言われてみればこれは「オーラ」を元に「物質化」しているのではなく、「水」を元に「物質化」しているわけで、正直、ツボネの能力が解説された時の"(自分が)やっちゃった感"は凄まじかった。
さて、気を取り直して話を進める。
以上のことから具現化系能力とは「オーラ」や「肉体=物体=物質」を元に「思念を物質化できる」能力と言えよう。
一応それを踏まえた上で定義を訂正するならば
→オーラや物体を元に、思念を物質化できる系統
としておくのが無難だろうか。
そして「思念を物質化できる能力」とは言っても、人間の能力の限界を超えるような神懸ったもの―例えば何でも切れる刀など―は創れない。
かと言って、多少良質の「実在するもの」を具現したところであまり意味もなければ、具現化物に用いられたオーラはAOPに含まれるため、具現化系は他系統に比べ戦いに関してバランスが悪いと言える。
しかしながら、「だから具現化系が弱い」という意味でもなく、具現化物に付加する特殊効果や制約と誓約により、操作系能力と同様に各々が「型にハマれば最強」になりうる。
◇手から離れた具現化物
Q:手から離れた具現化物は、離れた瞬間劣化するのか。
A:しない。
個人的な解釈では、AOPに内在されるオーラと外在するオーラで明確に分けた。そうしなければ、系統別のパワーバランスが滅茶苦茶になってしまうからである。
以前のバージョンではここで扱った箇所だが、【その2】AOP・EOP【念関連1】 を中心に【念関連1】にて扱ったため、そちらを参照。
◇具現化率
果たして100立方センチメートルの物質を具現化するには、100立方センチメートルのオーラが必要なのか。
ダミーとして、
相当数のビル(本人いわく50棟は余裕)を具現化していたが、
もし、このビル群の体積とコルトピのオーラ(AOP)の体積が等しいならば凄まじいことになる。
しかし、旅団内での腕相撲ランキングは、
このようになるらしい。
腕相撲の強い・弱いの要素を分けるなら―
肉体の強さ(BP)とオーラ量(AP=AOP)と強化系の威力・精度(SP)
―の3点だろう。
明らかになっているor想像される念系統と概ね一致し、コルトピのオーラ量が凄まじいことは読みとれない。
ただ、この「腕相撲」の件だけで考えてしまうと「コルトピがこうゆうことに興味がなかった」という逃げ道が残ってしまうのかな。
高校生の頃に少しかじったくらいの知識なので相当に怪しいように思われるが、印象は「E=mc^2」が近いのかも。
正確に採ると全然違うんだろうけど、その中の「質量とエネルギーの等価性」の印象流用するとそれっぽくなるのかな。
オーラとは即ち生命"エネルギー"なわけで、それを用いて思念を具現(エネルギーを変換?)してることを考えれば、高エネルギーは高質量を、低エネルギーは低質量を生成(具現)するように思われる。
それを頭の隅に置くと、『練』でオーラの質を高めていれば量が少なくとも大きな物は創り得る。
また具現系能力の『習得度』を考えれば、LV.1の能力とLV.10の能力で、1オーラあたりの具現化率が上昇してもおかしくはないかもしれない。
さらには、習得度と同程度で増減する『威力・精度』で見れば、具現化系能力者が100オーラで「100こっちん」作れるとすると、強化系能力者が「100こっちん」作るにはおよそ167オーラ必要になろう。
また、『制約と誓約』でリスクを背負ったり、利点を捨てたりすれば、その分効果は高まる。
よって、100立方センチメートルの物質を具現化するには、100立方センチメートルのオーラが必要になるとは限らず、具現化率は能力者や能力の性質によって大きく変化するものと採る。
◇遠隔操作型(リモート)⇔自動型(オート)
レイザー戦にて示された具現化物の遠隔操作型(リモート)と自動操作型(オート)の違い。
能力者が気絶すると消えてしまうのが遠隔操作型(リモート)で、能力者が気絶しても消えないのが自動操作型(オート)のようだ。
デスクトップPCとノートPCの違いを使って例えるなら、
電源(能力者)◆━◆デスクトップPC(具現化物)
電源(能力者)◆…◆ノートPC(具現化物)
デスクトップPCは、停電(=電源元異常)が起きれば一緒に落ちるが、
ノートPCは、停電(=電源元異常)が起きても内蔵の電池(充電)が残っている限り落ちない。
さらにこれを念に当てはめると、
遠隔操作型(リモート)=AOP内在・分散型=具現
自動型(オート)=AOP外在型(EOP型)=具現化→放出
ということだろう。
リモート型という言葉の通り、能力者の自由意思に基づいた指示が出せるため融通が利くが、
オート型は、内在されたプログラム(操作)によって動くため、融通が利かず、
リモート型はオーラの回収が可能だが、オート型はオーラの回収ができない(掛け捨て)といったところか。
ただ制約と誓約だったり応用により、「AOP内在型のオート」だったり、「EOP型のリモート」なんていう混合型もあろう。
◎無敵の具現物・ポットクリン
「無敵」のポットクリンは、神懸った具現物作れないのではないのか。
→操作系能力「ルール2」に反しない範囲での「ルール1」の類推適用。

『無害ゆえに無敵』
作中では非常に端的に説明されたが、操作系ルール2に反しない範囲でのルール1で説明できそうだ。
現実世界でもキャッシングにおいて、相手方に書面を交付しなければならない法律(貸金業法17条)が存在するが、ナックルは「相手に貸金(貸しオーラ)と利息を通知する事」をルールに組み込んでいる。
「相手に通知する機能」は相手に害をもたらすものではなくそれどころか、自らの能力の内容と攻略の糸口を与える事になり、相手のメリットになりうる。
そして、相手へのメリットは能力者にとってのデメリットになり、制約と誓約として能力の底上げになりうる。
すなわち、制約と誓約による能力の底上げを目的としながら通知機能を果たすポットクリンが壊れてしまった場合制約と誓約になりえない=無敵の具現化物である事、それ自体が制約と誓約なのだろう。
◇無敵の具現物ポットクリンについて・簡易まとめ
ルール2:絶対的ルールは創れない
に反しない範囲での、
ルール1:他人の創ったルールには干渉できない("除念"を除く)
であるから、無敵の具現化物・ポットクリンは成立する。
余談だが―
上記の理論で行けば、スポーツ等に用いる"道具"には無敵性を付与できよう。
サッカー、野球、テニス、バレーボール、ドッヂボール、なんでも構わないが、強化系能力者を代表として力の強い者が絡む度に道具が壊れてしまっては、そもそもスポーツ自体が成り立たない。
しかし、テニスならテニスで「ラケット」やら「ボール」やらを前提にしたルールがあるのだから、スポーツをやるにあたって大前提となる道具を具現化した場合には、無敵性を付与できよう。
しかしながら、スポーツ自体に―競技によってその確率は全く違うのだろうが―怪我のリスクや低確率での「死」が付きまとっているわけで、「無害」とは言えないのではなかろうか。
そこで、少し視点を変えて見る。
具現化物の「無敵性」と「無害性」は関係がないのではなかろうか。
ポットクリンの例では言えば、無害だから無敵なのではなく、壊れないこと(壊れないで相手に通知をし続けること)がルールだから成立したに過ぎない(操作系ルール2に反しない範囲でのルール1)。
むしろ、恐らく「有害」な「無敵の具現物」は可能なのではないだろうか。
ゲームでよくいる「無敵のモンスター」や「無敵の障害物」だ。
ただ、そいつを倒さないと絶対に先に進めないだとか、性質上その障害物を避けて通ること自体ができないならば、操作系ルール1に反して成立しえない、というだけの話である。
話は戻るが、例えば、
「マイクタイソン(全盛期)と1Rやるなら参加賞でも100万ドル、買ったら1000万ドルあげる」
と言われた場合、「怪我するかも」、「死ぬかも」なんてことは言われなくともわかるわけで、「怪我」や「死」は潜在的なルールとして内包されているとすることもできるのかもしれない。
まぁ、無敵の道具(死ぬかもしれない)も、操作系能力のルール2に反しないルール1で考えるのが楽かも。
◆変化系
→オーラの形状・性質を変化させることができる系統
というが従来の定義。また水見式から考えてみる。
変化系の結果は「水の味が変わる」だ。
具現化系と同じように、「オーラ」だけにではなく「物質」にもその力が作用しているのがわかる。
さて、それでは「水の味」とはなんぞや。
天然ミネラル水ならば、鉱物分やら微生物が溶け込んでいるらしいので―東京の水道水もおいしく頂ける"幸せ者"な私にはわからないが―原理的にはそれの味なのだろう。
では、その「味が変わる」とは何ぞや。
鉱物分や微生物の成分を変えているのだろうか。まぁ、なくはないのかもしれない。
ここで少し"変化系"から頭を離してみるが、「水」を甘くする時どうするか。 まぁ、身近な「砂糖」とかを入れてみますわな。
そして、ひょっとすると変化系の本質はこの「性質の付加」なのではなかろうか。
例えば、ヒソカの「伸縮自在の愛(バンジーガム)」で見ると―
「オーラの性質をゴムとガムに変えている」のではなく、「オーラにゴムの"伸びる"性質とガムの"粘着する"性質を加えている」
―ということで、オーラに性質を"加えている"だけだからオーラの元々の性質は残っていて非能力者には見えないことにもしっくり来る。
すると、もしかすると変化系能力者はONE PIECEの超人(パラミシア)系みたいなことができるのかもしれないね。
ヒソカ「ゴムガムのぉ~銃(ピストル)! どん!!!」
なんてやったら笑ってしまうけど。
戯言はさておき、もう1つ反省も込めて検討をしたい。オーラの「形状変化」だ。
本誌感想時と同じく、
No.325にて披露されたレオリオの能力からみていきたい。
性格、ゴン・キルア・クラピカとのバランス、能力自体の様相からみるに、レオリオの主系統は「放出系」で問題ないだろう。
ワープ先もしくは標的指定から、操作系も入っているだろう。
問題はこれだ。
オーラが拳の形をしているのだ。
こうだったら「放・操」でよかったのかもしれないが、
オーラの形状変化が入っているので、「空間ロケットパンチ(仮)」は「放・変・操」の能力ということなのだろうか。
―みたいなことを本誌感想時にやり、あれこれ言っていたのだが、やはり「オーラの形状変化」は「変化系に属する能力」で良いと思われる。
本誌感想時に「放・変・操」だと好ましくないと思っていた理由は「威力・精度」が原因だった。
仮にレオリオが1000オーラを用いたとすると―
「1000オーラ×1.0(放出)×0.8(操作)×0.6(変化)=480」―こんな計算式を浮かべていたのだ。
が、これがそもそもの間違いなのだろう。
今回の更新の「威力・精度」の箇所でも触れたが、その2つは同列で何に着目するかによってその言葉自体も変わりうる。
そして、そもそも「形状変化」はどんな下方修正が入り得るのか。
例えば、強化系能力者が1000オーラを刃状に「形状変化」するとそれだけで800オーラに減ってしまうようなことが起きるのか。どうも如何にも怪しい。
もちろん、それが「性質変化」ならばそうなりそうなのもわかる。
どんなに優れた「刃」像を思い浮かべても、その性質をオーラに「付加」する精度が最大で80%だから、斬れ味(威力)も80%=800オーラ分しか出ない、ということだろう。
そうすると形状変化は、単に「精度」なのではなかろうか。
まず、「0~9」までの数字を5秒以内に作れるようになることが最終目標、というように下方修正が入る要素として「変形速度」が浮かぶのだが、これは念の基本要素である「オーラの動きのスムーズさ」とも思えるため除外。
それならば、一番単純に「造形精度」なのではなかろうか。
形状変化をするために、数字の形状(PCで言うところのフォント)を思い浮かべるのだろうがその思念を80%でしか再現できないからディティール(細部)が甘い、といった感じだろうか。
では、さいきほどの計算式は―
「1000オーラ×1.0(放出)×0.8(操作)×0.6(変化)=800」
―となるのかと言えば、恐らくこれも違う。
1000オーラの内、念弾(?)に何割、操作プログラムに何割と予め分けることもできてしまうかもしれないからだ。
そして今回、改めて形状変化を完全に変化系能力として、昔のバージョンに戻したのは―、

ビスケが、系統別の修行の中で、ゴンの「形状変化」と「EOP化(?)」を見比べ、

ゴンが"放出系よりの強化系能力者"と判断していることへの有効な反論が見いだせなかったためでした。
以上のことから、改めて定義を見直すと、
→オーラや物体を形状・性質変化(付加)できる系統といった感じだろうか。
◆強化系

→ものの持つ働きや、力を強くすることができる系統
攻め・守り・癒しを一番効率よく補強できるため、戦闘において最もバランスが良いとされる。
水見式において示された「水の量が変わる」という強化系オーラの性質から、「増える」という正強化の他に「減る」という負強化が想像できるが、作中では圧倒的に正強化の描写が圧倒的に多い(負強化は梟のファンファンクロスなど)。
確かに強化系能力者の性格だとか、負強化(相手にもたらす場合は+操作系能力)のコスパを考えれば、自分を正強化してぶん殴った方がよいのと考えるのも当然かもしれない。
そして、ゴンの能力やビスケの能力から―、
その力を最大限に使うとき、細胞が活性化し肉体がピーク時の年齢に戻したように
―細胞の±強化もできるようだ。
ただ、若返ったら必ず正強化というわけでもなく、能力の「意図」や「対象」によっては正強化は負強化になりえ、その逆も然りだ。
また、「出す」と「出さない」が同時にできるように、正強化と負強化を共存させることで効果が向上させることもできるのかもしれない。
【念関連2】以上。
続いて今回を更新を用いて、明確な結論を出さずに終わった【念関連1】を補完する。
【その5】SOCその2【念関連1】

以前書いた【念関連1】の主に【その4】
と、今回の【念関連2】の【その1】
を基礎に置く。
とか言って、書いた自分自身ですら読み返すのが面倒なので重要なところだけここで簡単にまとめてしまう。
まずそもそも、SOCとは筆者(ばんぶー)が勝手に作った言葉で、『発』を用いた時に消費されるオーラ量を指す。
SOCなるものは、ゴンVSナックルの最終戦において示されたのだが、
ゲームで「メラ」を使ったらMP(マジックポイント)を2消費する様に、
ハンターの世界でも『発』を用いるとそれに応じたオーラが消費されるらしいのだ。
しかし、そこで大きな問題が生ずる。
何度も具現化物を出し入れするような能力者、つまりはカストロや特にネテロが詰むのだ。
1:Xオーラ→具現化 ★Yオーラ消費(SOC)
2:解除
3:"再具現" ★Yオーラ消費(SOC)
4:1~3ループ
ネテロはメルエム戦において、この4を数千回繰り返している。
「零」はオーラが少なくなればなるほどその威力を下げてしまうので、当然浪費は避けるようにしているハズなのである。
カストロだけなら、最悪「念能力者として未熟だから」という結論で、周りの言葉は気にせず逃げ去ることもできてしまうのだが、
半世紀前には最強の念能力者と謳われ、あの時点においてでも念の扱いに関してはトップレベルにあるだろうから何かしら理由をつけたいね。
―というのが以前書いた【念関連1】の主に【その4】 で、ちゃんと結論を出していないのだ。
元々【その0】 で書いた通り、急造で立ち上げたβ版みたいなものだったんですが、その所以は最終的な結論に今回の【念関連2】の【その1】 の発想+αを用いたかったんですな。
と、そんな感じでネテロ先生の念を上手く捉えることはできないのだろうか、というのが今回の趣旨。
作中描写に反しないことを大前提とし、
1:再具現時の消費量(SOC)がゼロ
2:"消費量(SOC)がゼロ"の代償がある
の両側面がありバランスがとれているとベター。
<もくじ>
◆停止条件付きの『発』
◆現に具現されていなくとも有効な『発』
┗ヒソカVSカストロ戦の意味
◆停止条件付きの『発』
操作系の『発』の一種で、『発』の効果の発生を将来起こるかどうか不確実な事実にかからしめるものをいう。
現実世界風に言うと、「大学に受かったら(=停止条件)、車を買ってやる(=効果)」等。
作中では、それらしき"発"が少なくとも2つ見受けられる。
ゲンスルー組の「命の音(カウントダウン)」である
クラピカの「律する小指の鎖(ジャッジメントチェーン)」ならば、

クラピカが定めた法を破ったとき(=停止条件)、鎖が心臓を握り潰す(=効果)。
ゲンスルー組の「命の音(カウントダウン)」ならば、

ゲンスルーが対象者の眼の前で能力についてきちんと説明したとき(=停止条件)、
取り付けられた爆弾のタイマーが作動する(=効果)。
クラピカの方はまた別の要素が出てきて大きく話が逸れるため、ゲンスルーの方で見てみる。
「命の音(カウントダウン)」は、対象者の爆破させたい箇所に触れながら「爆弾魔(ボマー)」と言うことで取り付けることができる能力だが、
"設置"されてから停止条件を満たすまでの間、どうなっているのだろうか。アベンガネの所見によると、肩につけれたら爆弾は「具現物」のようだ。
発動するまで『隠』が掛けられていた?
なるほど確かに、「ハメられ組<<<<<ゲンスルー」といった具合に両者間の力には大きな開きがあるから、ハメられ組が『凝』しても見破れなかった、というのは一理あるかもしれない。
―がしかし、ビスケがいる。
実力的にゲンスルーよりも下、というのはおよそ考えられないし、
怪しい雰囲気を感じたら何をおいても『凝』と、口すっぱくしていた彼女が、

あからさまに怪しいGI開始直後の勧誘や、情報交換の際に『凝』をしないとは思えない。
また情報交換の際の話ぶりからするに、少なくともアスタとハンゼ組の男には「命の音(カウントダウン)」が付けられているように思われるが、そんなアスタらを見て"何人か心当たりがあるようだわね"というのはあまりにおかしいだろう。
よって、"設置"されてから停止条件を満たすまでの間『隠』されている、というは無理がある。
つまり、元々の「停止条件付き○○」という言葉通りの解釈でよいのだろう。
現実世界風に言うと、まだ大学にまだ合格していなかったとしても、"受かったら車を買ってあげる"という『約束』自体は有効、ということ。
これを停止条件付きの『発』にあてはめるならば、条件が成就していなくとも『発』自体は有効ということ。
少し言い換えると、『発』自体は行われいるが、条件を満たしていないから効果が発生していない(=具現されていない)、ということ。
この箇所で触れたかったのは正にこれで、現に具現されていなくとも『発』として有効な一類型があるということだ。
◆現に具現されていなくとも有効な『発』
上記2例は共にEOP化された具現物であったのだが、AOPの場合どうなるのだろうか。
今回の【念関連2】の【その1】 で若干触れたのだが念の各要素は、
能力者→CPU
AOP→メモリ
POP→HDD
オーラ→データ
と捉えることができるだろう。
そして、現に具現されている状態ならば、
AOPに内在されているのだから、メモリにも乗っかっている状態だろう。
それでは、現に具現されていなくとも『発』として有効な一類型として考えるとどうなのだろうか。
ひょっとすると、メモリに乗っかったままなのではなかろうか。
『発』として未だ有効な状態だから、"再具現"が新たに『発』を用いたとも言えない。
だからこそ、SOC(発オーラ消費量)がゼロなのだ。
便宜的に、
現に効果が出ている(具現されている)状態を完具現
『発』はなされているが現に効果が出ていない状態を半具現
と呼ぶが、完具現の状態だとROC(ランニングコスト)が増加するのだろうか。
◎ヒソカVSカストロ戦の意味
趣旨からは脱線するのですが、もう触れる機会がなさそうなのでここで扱う。今回の半具現はヒソカVSカストロ戦での私の疑問を解決できるものかもしれない。

1:千切れた左腕を"完璧"に下アゴにヒットさせたから、カストロはしばらく自分の意志では動けない
2:心身状態が非常に不安定だから分身(ダブル)が出せず、飛んでくるカードを分身(ダブル)で防ぐ事はできない
一番の敗因は、
分身(ダブル)という"大変な能力"を覚えてしまったが為に―逆に他の能力が使えなくなってしまう―メモリ不足に陥ったこと。
しかし、私は2と3の間に疑問があった。
ヒソカへの警戒や恐怖心からか、カストロは元より分身(ダブル)での攻撃を主体に行っていた。
だからこそ、ヒソカの揺さぶり後のカストロはそれが加速することが予想される。
そのため、1の後の2の流れは何ら問題がない。
心身状態が不安定だから、高い集中力を用いるような能力は使えないのもわかる。
しかしながら、当人からすれば原因不明なのかもしれないが、分身(ダブル)が出ない以上、迫りくる攻撃に死を予見するだろう。ウイングの所見によればカストロは強化系。
すると、「負けたくない」そして「死にたくない」という原始的欲求と、生来の「強化系オーラ」が相俟れば、BP強化もしくはDP強化を成し得るのではなかろうか。
飛んでくるのは言ってもトランプカード。BPは大したこともないだろう(それとも特別製?)。

飛んでくるカードに用いられたオーラ量はさほど多くはないため、APもさほど多くない。
APやBPの少なさから、そのどちらかの強化(SP)が予想される。
それに対するカストロのBP+DP+SPを考えれば、無傷は難しいかもしれないが死にはしないように思われたのだ。
そこで、今回の半具現をぶち込む。
まずこの段階で、自分の読み違えに気づく。
どうも私はCPUとメモリをごっちゃしており、人間のように高度なものを作ったあまりそれに集中力を費やし過ぎ、他のことに頭が回らない。すなわち戦闘スタイルが単調化し、想定外の攻撃への対処ができないor遅くなる、と読んでいた。
だが、この読み方は「CPU側の問題」なのだ。CPUが弱いから容量の多いデータを上手く扱えないようなことを言っている。
あくまでヒソカが言っていたのは「メモリ不足」と「メモリのムダ使い」。
半具現の概念をぶち込んでいくと、カストロのは自らの意志で"解除"したわけではない。
単純に心身の状態が不安定だから、うまく能力が使えなかっただけなのだ。
つまりこれは、分身(ダブル)自体は有効だが現に具現されていない(効果の出ていない)半具現の状態と採れる。
【念関連1】の【その2】 にて―、
『発』に供せられ―解除しない限りは―自由に用いることのできないAOPをrAOPとし、
『発』に供せられてはいない、常に自由に用いることのできるAOPをfAOPとした(AOP - rAOP = fAOP)。
―という解釈上の言葉を創ったのだが、これに当てはめてみる。
すると、この時のカストロのAOPの一部は分身(タブル)に供されいる状態だ。そして半具現は"解除"ではないから、自由に使えるAOPすなわちfAOPに変化はない。
つまり、確かにカストロの生来の念系統と「死にたくない」という気持ちが相俟れば、カストロはBP強化もしくはDP強化を成し得た(実際にできたかはわからないが)。
しかしながら、ヒソカの繰り出した攻撃を十分に防ぐには、メモリ(AOP、この場合はfAOP)が足らないのだ。
1:カストロは脳しんとうで満足に動けない
2:心身耗弱により壁(ダブル)は作れず
3:もし頑張ってBP強化orDP強化をしても、その目的を果たすためのメモリ(fAOP)が足りないから
4:死ぬ
という論法なのだろう。
個人的にちょっとすっきりした。
途中脱線したので、最後にまとめ。
◇SOC簡易まとめ
SOCとは『発』を用いた時に消費されるオーラ量である。
中にはカストロの「分身(ダブル)」やネテロの「百式観音」のように、何度も『発』を用いているかに見える能力があるが、必ずしもその1回1回にSOCが発生しているとは限らない。
【念関連1】以上。
最後に、ちょっと恥ずかしい部分を直したいので30巻感想を部分的にやる。
H×H30巻 感想 へ。
H×H30巻 微感
◆HUNTER×HUNTER30巻
半年近く経って、単行本の感想ってのも変な感じなんですけども諸事情ありまして。
正確には30巻感想その1。その2は気が向いたらいつかやりたい。
でもあたし知ってる。大人のいつかは来ないって。
<もくじ>
◆本誌からの変更・描き直しの有無
◆マーメン?ビーンズ?
◆ジン「四つ…いや八つだな」
◆"それはどっちの" 解答
◆薔薇毒について
◆本誌からの変更・描き直しの有無
「私」が「あたし」になったり、「―」が「~」になったりと写植で微々たるものはありましたが、描写的にはないかと。
◆マーメン?ビーンズ?

ハンターズガイドでは「マーメン」とされていた彼が、ついに本編にて名が明かされる。
その名も「ビーンズ」。
まぁ、マーメンという名前に慣れてしまっているので、チードルが"ビーンズ氏"と言っていたことからも、「マーメン=ビーンズ」という氏名(ex.ゴン=フリークス) と緩く採っていいのかも。
◆ジン「四つ…いや八つだな」
結論から言えば紙の折り方のことを言っているのだろう。
が、とある事情から32巻まで見守ることとなった。
ジン:(既に書き終えた5つのルールを見て) 四つ…いや八つだな
ビーンズ:??
ジン:読んでくれ
ビーンズ:投票のルール…!?ですね… これは一体…!?
ジン:数日後には“十二支ん”が全員ここに集まるだろう おそらくくじ引きになる
ビーンズ:!? なぜそんな?
ジン:多数決や話し合いで解決しようとしたら死ぬ程長引く なにしろパリストンがいるからな
:パリストンから見れば、1/12でも自分により有利な方法になる可能性があれば上出来なんだ どっちにしろ勝ち戦だからな そして他の練習からすれば6/5になるって寸法だ くじほぼ手打ちさ
:言い出すのは…本命チードル 対抗でサッチョウ 穴がピヨン 大穴でカンザイか
ビーンズ:くじを引くのが私に…なると…?
ジン:このビルの中バイトとパリストン派のヤツばっかじゃん 他にいねーだろ?
:もしそのルールでおめーが納得するなら3つ折りにして当日まで持っててくれ
もしオメーが呼ばれなかったり呼ばれても紙の折り方が違っていたらオレは下を向いてるからその紙は燃やしてくれ (以下略)
ジンの読みはばっちり当たり投票のルールは十二支んの考えたものをくじで引くこととなり、くじを引く者としてビーンズが呼ばれることとなった。
そして、"呼ばれても紙の折り方が違っていたらオレは下を向いてる"とジンは言っていたが、
当日、ジンの顔は上がっていた(ビーンズを見ていた)。
―そうしてビーンズは、ジンの考えたルールが書かれた紙を引いた(出した)のだった。
まずこれには大きな問題がある。
ジンはビーンズに"3つ折りにして当日まで持っててくれ"と言い、ビーンズはその紙を当日引いた(出した)。
しかし、ビーンズの持っていた紙は"8つ折り"なのだ。
一応確認すると紙の折り方は、折り方次第で若干名称が変わったり折り目の筋も変わるのだが一番基本的な折り方は以下の通りである。

イメージ図は今回関わってくるものを挙げたが、言葉の意味としては「○つ折り=○つになるように折ること」である。
つまり、このジンの「3つ折り」という指示は履歴書などでよく使われる折り方で、一般的にくじ引きで使われるものでもない。またビーンズの手に隠れるようなものでもないだろう。
さて、ここからである。
ジンがビーンズに指示した「3つ折り」と「四つ…いや八つ」はリンクしているのかどうか。
リンクしていないならば―、
「四つ…いや八つ」は「現時点ではわからないジンが作ったルールに隠された意図」かもしれず、「3つ折り」に関しては「ぎゃはは、冨樫、折り方すらもろくに知らねーんじゃねーのwww」に行きついてしまうのかもしれない(ぶっちゃけるとその勘違いをしていたのが私なんだけども)。
リンクしているならば―、
作者ミスもありうるが、結論は写植ミスに落ち着くかもしれない。
まず「四つ…いや八つ」を"四つ(折り)…いや八つ(折り)"と解釈すると、ジンは紙の折り方を決めかねていたことになり、"いや八つだな"と言う通り、最終的に八つ折りを採用+その旨をビーンズに指示。
結果的に、ビーンズは"八つ折り"にされた紙を引いた(出した)、とキレイに繋がる。
また、1ページ前でジンに"四つ(折り)…いや八つ(折り) "と、正しい意義で迷わせていたのだから、次のページで作者が"3回折って紙を8つに分けること"を"3つ折り"と勘違いしていたとは考えられない。
つまり、作者の「3」と「8」の書き間違え、もしくは作者の汚く書かれた「8」が、黒鉛の薄れ等と相俟って、「3」に見間違えられたという写植ミスに落ちつく(後者に関しては前科があるので印象的には後者)。
しかして話は戻る。
基本的には一見明らかなものは「作者ミス等」で処理するのも可(それ以外はNG)というスタンスなのだが、今回の「四つ…いや八つ」は「3つ折り」と合わさった結果、どうにもこの30巻時点で断ずるのが難しくなってしまった。
―ということで32巻まで待ってみた。
あくまで結果論としてなのだが、しいてジンに隠れた意図があったとするとならば、
「チードル達がパリストンに勝つには十二支んへの票はとにかくすべてチードルに集めて、遅くとも(有効選挙の)2回目か3回目の選挙に懸けるべきだった(4回目では手遅れ)」
というところだろうか。
ここでもし、ごり押し解釈をしてゆくなら、
投票率95%以上だが得票率が過半数に達成しなかった場合、候補者は2回目で上位16名、3回目で8名、4回目で4名と絞られてゆく。
つまり、ジンの隠れた意図は4回目(候補者4人)では手遅れで、3回目(候補者8人)までに決めなければいけない="(デッドラインは候補枠が)四つ…いや八つ(の時)"?
しかし、どうにも違和感MORIMORIで、それこそ序数詞は「つ」じゃなくて、「人」とか「回(目)」とか別のものが良いのではなかろうか。
キャラの心の動きや言葉に関して入念に検討する作者のことを思うと、どうも採れる答えとは思えない。
◇四つ…いや八つだな 結論
「四つ…いや八つ」は折り目のことを言っており、くじにする紙がどう折られるかを考えていた。
関連して、「"3"つ折り」に関しては、作者の「3」と「8」の書き間違え、もしくは作者の汚く書かれた「8」が、黒鉛の薄れ等と相俟って「3」に見間違えられたのだろうか(写植ミス)。
◆"それはどっちの" 解答
東ゴルドー城にてピトーと相対するその直前、
ゴンはキルアに"行こう"と言い、キルアはそれを受け、
"それはどっちの"と疑問を抱いた。
当時私は、
カイトの生を信じた上で、"(カイトを)助けに行こう"(操作状態を解かせる)
なのか、
カイトの死を脳裏でわかっていて、もしくは死んでいるかもしれないという思いを押し込めた上で、
"(ピトーを)倒しに行こう"(殺しに行こう)
のどっちと採りキルアにとって光たるゴンが闇に染まりつつあることへの苦悩を描いているのかと考えていた。
そして、その答えは作中で明かされる(説明される)ことはないと思っていたのだが、30巻にてまさかの正式解答頂きました。

任務(チーム)としての、行こう
なのか
友達としての、行こう
のどっちの意味なのか、ということでした。
なるほど確かに、そう解答を貰うとキルアの一貫した苦悩に繋がって納得してしまった。
というよりも、思考の方向性が違いましたな。反省。
◆薔薇毒について

"薔薇には毒があった
開花の瞬間大量に撒き散らされる薔薇の毒が類似する他のものより優れていたのは―
開花地との距離によって「運悪く」爆死を免れた者の体内に効率よく取り込まれ、
迅速に内部を破壊すると同時に被毒者の肉体が毒そのものとなり新たな毒を放出しながらやがて死に至る
―その毒の量と死ぬまでの時間が実に絶妙で大量の連鎖被毒者を生み出せる点にあった
要するにこの上無く非人道的な悪魔兵器だったのである"
気になるのはその毒の威力(感染力・致死率など)だ。
今回の被害者は―
選別の過程で、人民47万8594名+兵士1万2905名
プフ催眠覚醒後24時間以内に体調を崩し死亡した人民4万6613名
―とのこと。
注目すべきは、"プフ催眠覚醒後24時間以内に体調を崩し死亡した人民4万6613名"。
ニュースなどでは"特殊な薬品によって心身の自由が奪われた"とされていたのが、"プフの催眠"と述べられていることから、この発表は(読者も含め)事情を知る者へのものだと思われる。
また"最終的にはミニチュアローズ含む破壊兵器によって爆殺される予定だった"とニュースでは言われてた。
果たしてこの"人民4万6613名"は薔薇毒で死んだ者達なのか。
・催眠覚醒後の死亡者=連鎖被毒者?
発表が身内向けだったとしてもネテロ派に属する者から発せられたものならば、武道家たるネテロの名を汚さないために「配慮」されたものかもしれない。
また、ハンターが非人道的兵器を用いたことが世間に知られるのもおいしくないだろから、ネテロに蟻討伐を命じた御偉いさん方が強い根回しをしたのかもしれない。
つまるところ「発表は大嘘」っていう解釈。
ただ、どうにも疑問は大きい。
そもそも、それだけの連鎖被毒者が出て入れば医療機関や避難先での混乱は必至で、いかに強い根回しやら、かん口令を敷いたとしても隠し通せるものなのだろうか。
またこの解釈では、既に毒化が始まっていたユピーやプフそして王と近距離にいたウェルフィンやパーム、王宮敷地内に居た5000人の半人半獣(繭)は感染しなかったにも関わらず―、
城外にいた人民らには感染した、ということになってしまう。
「プフ経由で感染した」
ということになるんでしょうけど、やはり人民の密集度合いから見ても"連鎖被毒"したにしてはむしろ4万6613名は少ないように感じられる。
・催眠覚醒後の死亡者≠連鎖被毒者?
おおまかに考えてみる。
ゴン・キルアの会話から、東ゴルドーの人口は500万人。
選別の過程での死亡者を引いて450万人程。
東ゴルドーの平均寿命などわかる由もないが、ディーゴの圧政からするにさほど高くないだろうということで適当に60代。
王宮前にいた人民達の様子から老年層は決して少なくない様に見受けられるため、適当だが少なくとも全人口の10%はいるだろうと仮定(計算楽だし)。
すると、王宮前に45万人程度は老年層がいる。
そんな老年層が、
慣れない長距離移動に加え、
銃火器を持った兵士からの怒号や、長時間に渡る密着状態での集団行動を強いられ、
極めつけには催眠(操作)で強制的に立たされ続けていたのだから、肉体的・精神的ストレスはその限界をとうに超えてると言っても過言ではないだろう。
老年層だけで考えると
「その約10%が極度のストレスと疲労によって覚醒後に変調・死亡した」
となるのだが、さらにそこに子供や体の弱い者、何らかの疾病を抱えている者達を考慮すれば、その分パーセンテージ下がり、受容できるレベルにあるように思われる。
よって、私の解釈では催眠覚醒後の死亡者は連鎖被毒者ではない、とする。
さて、そうすると薔薇毒による死亡者はユピー、プフ、王、コムギ(死亡順)の計4人になる。
性質を抽出してみると―
("開花の瞬間大量に撒き散らされる薔薇の毒…は―
…体内に効率よく取り込まれ、迅速に内部を破壊すると同時に被毒者の肉体が毒そのものとなり新たな毒を放出しながらやがて死に至る
―その毒の量と死ぬまでの時間が実に絶妙で大量の連鎖被毒者を生み出せる…")
―薔薇は、
1:開花(毒散布)
2:吸収
3:体内破壊+毒化("ミニュチュア"ローズ化)
の三工程で被毒し、
4:"ミニチュア"ローズ開花(毒散布)
5:吸収
と、連鎖被毒するようだ。
さて、それでは改めて考えたいのだが、どのように感染していくのだろうか。
大元の"貧者の薔薇"の方は、爆煙で成っている上"撒き散らされる"と表現されているので、毒キノコの胞子のように撒き散らせたものを吸ったりしているのだろう、と想像に易いのだが―、"ミニチュア"ローズの方はどうなっているのか。
"被毒者の肉体が毒そのものとなり新たな毒を放出"する、というが被毒者の体がボロボロと崩れている描写もないので、キノコのように胞子をボフっボフっと毒を撒き散らしているわけでもないだろう。
そして、フェルフィンやパーム、そしてプフの死体の周辺に立ち尽くしていた人民達に連鎖被毒しなかったことを考えると、「"接触"感染」なのかもしれない。
厳密に言えば「接触感染」、「飛沫感染」、「飛沫核感染」、「血液感染」など諸々含んでしまいそうなのだが、"毒"に汚染されたものを吸引、あるいは皮膚や粘膜が接触することにより体内へ吸収されていく、とすると大元の"貧者の薔薇"の開花→吸収ともほぼ一致するのかも。
プフの周囲に居た人民らに連鎖被毒しなかったのは、
プフと人民の位置と風向き、そして風力。
さらには催眠状態にあったがために呼吸が浅かったことに起因するのだろうか。
―あるいは、大元に比べ"ミニチュア"ローズは毒性(?)が弱く「飛沫核感染」は起きないのかもしれない。
また、これまで被毒の順番を
1:王→2or3:ユピーorプフ→4:コムギ(連鎖被毒)
と思っていたんですが、本当は
1or2:ユピーorプフ→3:王→4:コムギ(連鎖被毒)
なのかもしれない。
薔薇の真下の爆心地の中に居た王には、どうも毒が届かないように思われる。
上昇気流で舞い上がってしまうだろうし、岩が赤黒く溶けてるということは800~1000度前後はあろう。
薔薇毒の詳しい成分はわからないが、どうも燃えるか毒性を失いそうな気がする。
―少なくとも爆心地脱出以降、それも上昇気流の関係で爆心地付近には舞い落ちて来ないだろうから、毒入りの"お食事"もしくは移動(飛行)により既に毒が飛散されたところに行ったことが被毒の原因だろう。印象的には前者のような気がしている。
最後にまとめると、薔薇の毒は大元もミニチュアの方も感染経路は"接触"。
しかし、ミニチュアの方はその母体となる人間の性質上範囲が著しく狭くなり、寝食を共にする者だとか、変調をきたした被毒者に親身になるものを殺してゆく、正に「悪意の進化」とも言える悪魔兵器に変貌を遂げたのだろう。
30巻感想以上。
更新&お蔵入り
遅ればせながら2013年明けました。
ご縁がある方は今年もよろしくでございますよ。
とか言って、正直そこまで活動しない気がモリモリしている。
さて、早速ですが本題です。
最新刊(32巻)収録内容と、特別読切から受けた印象、2ndでの検討を反映させるべく更新しました。
-------------------------------------------------------
ver.2nd:【その1】念 四大行ほか【念関連2】
ver.2nd:【その2】念の威力・精度ほか【念関連2】
ver.2nd:【その3】念 系統別①(操・放・特)【念関連2】
ver.2nd:【その4】念 系統別②(具・変・強)【念関連2】
ver.2nd:【その5】SOCその2【念関連1】
ver.2nd:H×H30巻 感想
-------------------------------------------------------
ちなみに31巻・32巻の更新は今のところ予定しておりません。
本誌感想時と比べて―多少プロセスは変わってるものの―結論自体に恐らく変化がないのと、32巻ちゃんとはしばらく顔を合わせたくないからです。
本当は30巻も一緒に放置するつもりだったんですが、ちょっと恥ずかしくて部分的にですが更新しちゃいました。
ところで話は変わりますが、個人的には考えの変遷が見れて面白いかと思っていたのですが"見づらい"というご意見も頂いていたので、今回の更新に伴いバージョンの古い以下の記事がお蔵入りしました(過去記事にリンクして下さっていた方ありがとうございました、嬉しかったです。そしてすんません)。
-------------------------------------------------------
'11/08/05 1st-2:念 四大行ほか
'11/08/05 1st-2:念の強度・精度ほか
'11/08/05 1st-2:念 系統別①(操作・放出)
'11/08/05 1st-2:念 系統別②(具・変・強・特)
'11/11/29 1st-3:【修正】【念の威力・精度】【オーラの変換】
'12/01/24 1st-4:念 四大行ほか
'12/01/24 1st-3:念の威力・精度ほか
'12/01/24 1st-4:念 系統別①(操・放・特)
'12/01/24 1st-4:念 系統別②(具・変・強)
'12/01/24 1st-4:リンクの差し替え
'12/02/17 1st-4:【再・修正】ダメージ算出と念の威力・精度【ver.4】
-------------------------------------------------------
※分類の意味
1st-1:AOPとEOPの区別ができていない(手から離れると具現化物は劣化する)
1st-2:ダメージ算出において、威力・精度を各々加味
1st-3:ダメージ算出において、精度を除外
1st-4:ダメージ算出において、威力と精度を同一視
2nd:fAOP、rAOP、EOP、ROC、SOCの創出・追加に加え、念関連を最新刊情報まで更新
更新以上。
明日から仕事・学校の方も多いと思いますが、また頑張りまっしょい。
-------------------------------------------------------
2013-01-18 追記
HUNTER×HUNTERとは関係ありませんが、気恥しくなってしまう古い記事の一部も蔵入りさせました。
【未視聴者 注意】緋色の幻影(ファントム・ルージュ) 感想【H×H映画】
昨日公開の映画『緋色の幻影(ファントムルージュ)』、早速見て来ました~。
少し気持ちを落ち着かせるために1日置いたんですが、恐ろしい程に記憶が飛んでる件。
まぁ、せっかく見たので何かしらつっついてみる。
まだご覧になっていない人には『アレ』になるので、スクロールにご注意を。
<もくじ>
◆0巻関連
◆映画の成り立ちほか
◆感想1
◆感想2
◆0巻関連
収録内容は大きく分けて以下の3つ。
・クラピカ追憶編
・冨樫義博一問一答(7問)
・キャラクター設定等(アニメ・映画関連)
どうせ適当に答えてくるだろうと思っていた一問一答でしたが、
思ってた以上に―作者の心情がよくわかる―いいものだったように思えます。
特にQ3は、蜘蛛の成立とその意義に関わり得る重大な情報を頂けたと思う。
何気に妄想が解釈たりえるんじゃないの。
一問一答の具体的内容については、他の方におまかせ。
◆映画の成り立ちほか
◎映画の成り立ち
そもそも今回の映画は、10年前にお蔵入りしたネーム(クラピカ追憶編のベース)に着想を得て作られたオリジナルストーリーと聞いて居たんですが、ちょっとニュアンスが違うのかも。
パンフレットの情報を元にもう少し紐解くと、脚本を担当した米村氏が、
"人形を使った別なクラピカの過去の話と共に、元幻影旅団のオモカゲを敵役として、クラピカの眼が奪われるという話"
を書いていたところ、週刊少年ジャンプの編集担当である齊藤氏から
"実はこういうものがあるんです"
と10年前にお蔵入りしたネームを見せてもらい、元々書いていた過去話に「クルタ村での話」が加わった様子。
つまり、着想を得た云々ではなく"オリジナルストーリーに作者のネームを部分的に貼り付けたのが今作"と言えるのかも。
◎時系列+α
「ヨークシン編」直後(13巻No.119と120の間くらい?)のパラレルのため―、
ゴン・キルア:「四大業」習得程度
レオリオ:「纏」習得程度
クラピカ:対蜘蛛特化だが、概ねの念を習得
―4人はこの程度の状況。
◆感想1
「0巻」貰うついでに見た感じ、言うなれば「ビックリマンチョコ」の「チョコ」のノリで見たんですが、まぁひどい。
監督曰く、"原作のある作品"を手掛ける時は"原作者が一番喜んでくれるもの"にしたいらしく、今回は原作を何十回も読みなおし理解を深めて臨んだらしいんですが、どの口がほざくのか小一時間は問い詰めたいところ。
しかし、笑う気もないのに「笑わせてみんしゃい!」と高圧的な態度を示すが如く、ハナから否定の気持ちで入るのもよろしくないわけで、ちょっと「冨樫さんがオモカゲの能力を考えた」体で見てみる。
まず、オモカゲの能力について。
オモカゲ自身は特質系能力者で、ノブナカは"人の心に潜りこみ、その者が最も執着する人物を人形として創り出すことができる"みたいなことを言っていたと思う。
ただ、ノブナガの心からウヴォー、パクノダ、陰獣が創られていたのはどうゆうことなのだろう。
本来的にはむしろノブナガの心から"最も執着する人物"を創れるとしたらそれこそ"クラピカ"なのではなかろうか。
パンフレットによれば"人の心に潜りこみ、その人物が最も執着する出来事から人形を作り出す"とある。
やんわり包むと最も固執している「"ウヴォーが死ぬことになった"ヨークシン事件」の記憶の中で強い輝きを示す者を人形として創り出しているのだろうか。
そして肝心の創られる人形の性質だが、記憶や念も持つがオモカゲの命令には逆らえないことと、段階があることだろうか。
一段階目は、瞳を持たない状態。人形の出来は"瞳"で全て決まると言っても過言ではないようで、いわば魂のこもっていない不完全な状態。
二段階目が、瞳を持つ状態。しかしながら、瞳を持っていれば即ち完全というわけでもなく、その人形に合致した瞳でないと人形としての完成度は低い様子(威力・精度が上がらない?)。だが、イルミ(人形)と正反対な性質を持つゴンの瞳が"逆に合う"とされたように、何をもって"合っている"のかはいまいちわからない。まぁ、操作系能力の物体操作と絡めて考えれば、術者が人形と瞳が合致しているように感じればそれへの愛着も増すし、より威力・精度が上げられるのだろうか。
また、劇中で示された人形の創り方にも2パターンあり、イルミ人形のように「実際にある人形に投影(?)させて創る」ツボネ式(?)と、「オーラから創る」従来式がある様子。
そして最後(?)の能力として、創った人形を取り込むことで(?)、その人形の『発』をオモカゲ自身が用いることもできる。
まとめるとオモカゲの能力は以下の4つに分類できるだろうか。
1:???…対象人物の心への侵入?
2:ソウルドール(?)…一段階目の人形創出
3:???…瞳の強奪による二段階目への移行(イルミ人形とかが眼を合わせた時に何か言ってたが聞き取れなかった)
4:ドールキャッチャー…人形を取り込むことで、オモカゲ自身も人形の『発』を使えるようになる
いまいちわからないのが、1と2。
3ならば一定の距離内で一定時間、人形と瞳を合わせる(瞳を覗きこませる)とかが、それっぽい条件になりそうだがどうやってオモカゲは相手の心に潜入して、特定の人物を引き出しているのだろう。
パクノダみたいに「対象者の体に触」って、「質問を投げかけることで、目的の原記憶をすくいと」ったりしてるならばわかるが、それらしき質問や会話をしていたようにも思えない。
1と2を劇中で行われたのは恐らくキルアのみ。
ノブナガに関しては"以前に侵入された者"として処理しうる領域があるため除外。
すると…、対象を"オモカゲの眼で見る"ことと、対象に"自分を触らせる"ことなのかもしれない。
"自分"というのは、オモカゲの肉体そのものでも有効だろうが、キルアの状況を見ればオモカゲの眼をハメ込んだ人形(もしくはレツ限定)でも可能なのかもしれない。
まず、"オモカゲの眼でみる"ことだが、
パームの「淋しい深海魚(ウインクブルー)」が、"右目で見る"だけで監視対象とすることができることを思えば、第一条件としては有効のように思える。
続いて"触らせる"だが、どのレベルなのか。
一方的にぶつかるだけで良いなら、街中で何も知らぬ子供(の人形)を装えば、できてしまうように思われる。
しかし、オモカゲは"旅団の人形を創るため"にわざわざ入団したらしいので"相手の意志で触らせる"方がまだいいかな?
ただ、身内(流星街の人々)に"笑顔で握手を求めながら自爆"する連中がいるくらいですし、一見何ら害意を持たぬ子供に見えても、わざわざ"ぶつからせる"なんてマヌケなことはしないか。
すると"子供の人形"とかを使って条件を満たすのは難しいから、敢えて入団して(自分から近づいて)"オモカゲから団員に触る"か"旅団からオモカゲに触らせ"ようとした、ということだろうか。
ただ、どうにも"自分から触る"のか"相手から触らせる"かで決めかねてしまうね(合ってるかはわからないが)。
まぁ劇中でレツ人形が自ら触りに行こうとしていた感じはなかったように思われるので、ひとまず後者で採ろうか。
改めて振り返ると、
1:???…対象人物の心への侵入?
└オモカゲ自身の眼による観察
2:ソウルドール(?)…一段階目の人形創出
└対象者にオモカゲ自身、もしくはオモカゲの眼が入った人形(レツ限定?)に触らせる
3:???…瞳の強奪による二段階目への移行(イルミ人形とかが眼を合わせた時に何か言ってたが聞き取れなかった)
└瞳のない人形と一定の距離内で瞳を合わせる(瞳を覗きこませる)
4:ドールキャッチャー…人形を取り込むことで、オモカゲ自身も人形の『発』を使えるようになる
こんな感じになるのだろうか。
能力だけでみるとまだ、特質系独特の「アレ」で納得せざると得ない部分があるのだが、実際の劇中での使われ方を見るとどうにも苦しいところが散見される。
例えばウヴォーだが、そもそもウヴォーの形をした念獣(?)をオモカゲが遠隔操作しているのではなく、ノブナガの心を元に創られた「ウヴォーそのもの」ようなもので、当時の記憶も念も全て持ち合わせており、それにイルミが針を刺したが如く強い命令を出しているのだ。
かといって、ゴレイヌのリモートのように壊されたら消えるわけではなく、壊されても―少なくともしばらくは―そこにあり続ける。
また、オモカゲが「束縛する中指の鎖(チェーンジェイル)」に拘束された時、ドールキャッチャーされた人形は消えたが、その他の人形は確か残っていた(だいぶ記憶あやふやだが)。
『絶』とは、そもそも精孔を閉じることと体外に出ていたオーラ(AOP)を0にすることだから、通常の人形は外在型(EOP型)で、ドールキャッチャーは再AOP化なのだろうか。
段々と怪しくなってきたが、以上のことからオモカゲの人形は一定の命令下で自由に動く、いうなれば、ある程度の自由が利くオート(自動型)で外在型(EOP型)なのだ。
そもそも系統的にソレが得意ではないのだろうが、それ以上に使われているエネルギー量もハンパではない。
まず具現(SOC1)、それも各々の人形が念を自由に使うのに十分なオーラを付与(内蔵?)、さらにそこから十分なオーラを持たせたまま切り離す(SOC2)のだから、恐らくウヴォーの人形1つだけでも少なく見積もっても1万オーラは使っていると思われる。
そんな人形をウヴォー、陰獣(3人か4人)、パクノダと湯水のように創り出すのだから、オモカゲのオーラ量は凄まじいのだろう。
そして、そんな人形の中でもウヴォーの眼を埋め込まれたウヴォー人形は劇中でも最高の完成度を誇るのだろうが、『超破壊拳(ビックバンインパクト)』でゴンらが泊っている宿を一撃でふっ飛ばしたかと思えば、四大業レベルの念しか習得していないゴン・キルアに通常の打撃では大きなダメージは与えられない。
その一方で、"強化系"の居合の達人ことノブナガさんの斬撃には何度も耐える。
なるほど、ゴンやキルアは眼を奪う必要があったから、本気で殴って殺してはいけないし、ノブナガも生前となんら変わらない声や様子に逡巡してしまって本来の力を出せなかったのかもしれない。
じゃあ、なんで宿にビックバンしてもうたんや。宿の倒壊で死んでもうたらどないするんや…。
いやいや、その程度の死んでしまうようなら、レツに相応しい瞳なわけないじゃないですか。いわばテストですよ。
ノブナガが最後、居合と見せかけて謎の連撃を放った時、体はそれに耐え体に痕が残るだけだったのに、首だけみごと落とせたのは何でや。
いやいや、人形には心と意志がある。いくらオモカゲの命令に逆らえないとは言え、心が乗らなければ『錬』もなければ『練』もない。
命令に逆らえなくとも、「右」に対して心で「左」と思えばそれはほんのわずかな時間かもしれないが挙動は遅れる。
ノブナガはウヴォーの体の強さに生前のソレを重ねながらも、自分の刀で痕をつけられることからウヴォーの意志を感じ取り、迷いを打ち消し相棒の首をハネたんや。兄ちゃんもそうゆう切ない気持ちわかるやろ?
そうか、いくら人形とは言え心があるから、出した命令にその人形が反発してしまうと、適合する瞳を持っていても本来の力を出せないことがあるか。
じゃあ、イルミ人形はどうなんです?イルミの心からすれば、人形の館での最終戦においてでもキルアを攻めきれない(殺せない)のはわかります。
でも、ゴンに対してはどうなのでしょうか。イルミの心情的にもあの時ゴンを殺してしまえば、非常においしかったと思うんです。望んでいた闇人形の第一歩に成りえる上、真にゴンを殺したのは自分ではないんですからキルアが自分を嫌うことにも繋がらない。Wチャンスですよ、これ。
オモカゲの命令とイルミの意志は合致して、本来的にゴンの瞳とその肉体(人形型)が合っていなくとも、それなりの力を発揮できるのではないでしょうか。
人形の館で、手をシュビビビって連続突きしてみたり、シュバババって連続蹴りしたりしてましたけど、渾身の力込めて殴れば、四大行習得レベルのゴンなら余裕でヤれるのではないでしょうか?
致命的なダメージすら与えられないのは何故なんでしょうか?
あ、あと、ドールキャッチャーっていう、クロロの上位互換みたいな技をもってるオモカゲですが、それまでフランクリン人形に「俺の両手は機関銃(ダブルマシンガン)」をさせて自分は自由にしていたのに、
わざわざフランクリン人形をドールキャッチャーして、自分で「俺の両手は機関銃(ダブルマシンガン)」したのってなんでなんです?
フランクリン人形にソレさせといて、自分は別の行動した方がよくないですか?
ああ、瞳がない状態のフランクリンにさせるよりも自分で用いた方が威力・精度が高くなるんです?
そうですよね、特質系なのに十分すぎるレベルでEOP化できてるみたいですし、持ち前のオーラ量がありますからね…。
の割に、四大業習得レベルのゴンとキルアに盾みたいの出されて防がれちゃうんですよねぇ。
この時点で『堅』は習得できてないですけど、天空闘技場でズシが『練』したオーラすべてを『凝』してるのを見てますから、土壇場での『練+凝』ですかね。
「クラピカの道を作る!」という強い『錬』を感じとれますし、劇中で描かれた友情パワーも加味したら1000~1300オーラ前後はあるんですかね…?
でも、二人共無傷ですよ…。
「俺の両手は機関銃(ダブルマシンガン)」ってそんなヌルいんですかね。
とまぁ、そんな感じで途中茶化しましたが、要は『念』じゃないんですよ、アレ。
というより、『念』で考えちゃいけないんです、たぶん。
制作側的には色んなことができる超能力的なナニカで、AOPとかEOPとかROCとかSOCとか、んな細かい概念は一切ない。
オモカゲの能力も「人形に命を吹き込む」という言葉通りに、ウヴォーを人形として新たに生み直した(喚び戻した)程度の気持ちで、『召喚獣』とかに近しいんじゃないのかなぁ。
だから人形の活動エネルギーとかオーラとかもオモカゲが与えてるとかそうゆうもんでもなく、『召喚獣』自身の物なんだと思う。
映画を見てる最中、出来る限り好意的に見ようと思いつつあれこそ想いを巡らしていたのだが、庇いきれなくなってしまった。
◆感想2
あまりにネガティブすぎるのも好きではないので、一応の"気持ち"をほんのりと置いてきたが、ここから素直な本感想。
「お前ら根本的に念を理解しようとしてないだろ」
というのも然ることながら、ゴンとキルアの友情を履き違えてないだろうか。
開幕のハンサイクロペディア(?)の段階でも十分すぎるほどのヤバさは感じ取れたのだが、最初の飛行船でのやりとりってセリフそのままに「ゴン(♂)とキルア(♂)」じゃなくて、「ゴン(♀)とキルア(♂)」でも成立しちゃうでしょ。
男同士の友情ってそうゆうもんなの?12歳くらいの男の子達の友情ってそうゆうもんなの?
「かわいいは正義」、「かわいければ何でもおk」という最近流行りの風潮に塗れた毒々しい何かを垣間見た気がするよ。
それをやることによって壊れるものがあるってわからんのかね。
そんな詳しいわけでもないけど、ジョジョアニメとハンタアニメ、どうして差がついたのか…慢心、環境のry)
泣けてくるよ。
そして、よくわからなかった疑問点。
途中、何回か私の近くにいたお子さんが泣きだしちゃったりしたので、聴き逃した(見逃した)だけかもしれないけど、結局のところオモカゲの裏切りってなんだったんだい?
クルタ族虐殺事件云々の真相も、クラピカの質問に対して「パイロに聞けばわかる」って言ったっきりで、パイロさん、特に言及してなかったよね…?
クルタ族の村に遺された『例のメッセージ』は、何故か即ちイコール「旅団」とレオリオは認識していたような気がするけど、そこもよくわからんかったなぁ。
特別読切の後編感想時にもちょっと触れたけど、オモカゲが能力を使って流星街の住民を襲い「クルタ族vs流星街」の構図を作り、蜘蛛が"お宝強奪"ついでに"慈善活動"したのかねぇ。
ただ、「0巻」で示された「クロロが自分から立候補して蜘蛛の団長になったわけじゃない」ってのを元に妄想してたら、蜘蛛って流星街の「一機関」的な役割を果たしているというよりも、ONE PIECEでいうところの『王下七武海』的な意味合いあるのかも、とか思ったり思わなかったり。
…加えて、何か今年中のハンタの再開すらない気がする。
同じく「0巻」Q3で触れられていたけど、
"自分の意に沿わずに決定された"場合、冨樫さんは"無視するか、ふてくされてダレる"らしいんですが、
このキルア、そのまんまwiiでドラクエ10やってる冨樫さんだもんなぁ。
パンフレットの一番最後にもう1枚描き下ろしのカラーがあるんですが、
(一応、大人の事情でモザイクかけときます)
やばすぎるだろ、これ。
わかりますかね、文字の下書きの線すらちゃんと消してないんですよ。
32巻発売時、私も相当効いちゃっておこでしたが、冨樫さんも相当レベルでおこでしょ。
あかんよ、これ。
それも、映画第二弾やるんですって。
もうそれだけで背筋がぞわぞわしちゃうんですけど、どうやら新アニメでカイトって出ていないらしい。
今回のアニメがGI編までだから、まぁわからなくもないんですけど、そんなカイトが今回の映画のエンドロール?でチラっと出てきたんですよ。
それも、映画第二弾「続報を待て!どどん!」みたいな感じでネテロが大々的に出てくるわけですよ。
まさか、第二弾蟻編じゃないよなぁ…。。。
でも、10巻相当に加え、カイトとの出会いをねっちり描くんでしょうから2時間枠?じゃ足らないよなぁ。
蟻編とGI編の間を描くのかなぁ…。
何にしても誰得映画になりそうな上、販促関係で冨樫さん狩りだすわけでしょ?
オワタ\(^o^)/
最後に改めて感想を述べるなら原作好きな人は見ないことを勧めます。
また、映画見て何か気が抜けてしまった人には何となく相対性理論のパラレルワールド 勧めておきます。
帰りの電車の中、何故か頭の中でこの曲がずーっとループしてて、映画を見た後のもやもや感と相俟って不思議な気持ちを味わえました。
【part2 未視聴者 注意】緋色の幻影(ファントム・ルージュ) 感想【H×H映画】

【未視聴者 注意】緋色の幻影(ファントム・ルージュ) 感想【H×H映画】
の追記をしたかったんですが、案の定amebaブログの容量をオーバーしたため、別記事で挙げました。
◆クルタ族虐殺事件の真相+α
誰も答えてくれなかったが、反応から察するにどうも私が見逃した(聴き逃した)とか意識が飛んでたとかではなく、そもそも劇中で「オモカゲの裏切りの内容」や「クルタ族の虐殺事件の真相」自体語られていない様子。
…それってすごすぎないか?
読切の時にも触れた箇所ではあるのが、映画で色々情報を頂けたのでそれを踏まえた上で改めて考えてみる。
まず、大きく【映画視点】と【原作視点】で分ける必要がある。
ただその前に。
思い返してみれば、予告CM等の中で劇中では実際になかったように思われるシーンがあるので、どうも予告CM等限定で用いられたシーン・描写があるくさい(クラピカが目に包帯をしながらダウジングチェーンぶらんぶらんするシーンなかった気がする)。
しかし、いい具合に映画の記憶も霞みがかり、私自身の中で映画、予告CM等そのどちらで見たか、区別が付かない。そのため、仮に予告CM等限定のシーンがあったとしても、それも映画シーンと推定する。
まず、どんどん記憶が逃げて行く映画視点から。
・旅団に裏切り者が居た(オモカゲ)
・シーラとは明言されていないが、クルタ村の近くまで近づいた者が居た
・クルタ族虐殺事件は起き、メッセージが残された
<情報整理>
・オモカゲの一番の目的は「レツに合う瞳」を探すこと
・しかし持ち前のコレクター気質から気に入った人形を作ることもままある
・オモカゲは旅団の人形をコレクションに入れるため入団
(どうも映画制作陣はオモカゲを「純粋悪」とは描きたくないようなので、本来の目的は自らの活動範囲を広げること、だったのかも)
・5年程前、「クルタ族虐殺事件」発生・発覚
・2・3年前、お気に入りの旅団の人形が入手できたため、オモカゲはヒソカと交代で退団(死亡)
・しかし、二人の戦いは仕組まれたものでヒソカが倒したのは人形だった
・ヒソカは"もちろん"それに気付いていたが、ここで殺すには惜しいと思ったため旅団には知らせず
・→映画へ
さて、「オモカゲの裏切り」とはなんぞや。「クルタ族虐殺事件の真相」とはなんぞや。
オモカゲの本来の目的を考えれば、どこかでクルタ族という変わった"眼"をもつ種族の噂を耳にしたら欲しくなりそうだ。
キルアへのソウルドールの例を考えれば、村への来訪者(シーラ)は、どうも「オモカゲの人形」のように思われる。
後に続く、"旅団を敵に回す"だとか"旅団の裏切り者"を考えれば、クルタ虐殺事件自体がオモカゲに仕組まれたと考えた方がしっくりくる。
かと言って、オモカゲは緋の眼を入手できていないため「旅団の人形」を用いて自ら滅ぼした、というわけでもなさそう。
また、シーラ人形を使ってクラピカもしくはパイロの記憶からクルタ族の人形を創り(ソウルドール)、流星街を襲撃させた、という流れも難しい。
ソウルドールだけでは瞳のない人形しか作れない。
そのためクルタ族の証明たりうる"緋の眼"なしに、つまり"変わりの眼"をハメこんだ人形を使って流星街を襲って、
"わいは、○○町×丁目に住んでるクルタ族や!悔しかったらいつでもこい!"
というのもありえないだろう。
むしろ、シーラ="元"は流星街出身の人間=ソウルドール(2段階目)と採って、ボロボロの状態で流星街に戻って、
"クルタ族に○年間、拉致監禁された上、××××されていた"
と証言するだけでいいのではなかろうか。
(原作では同胞の3年間の不当拘束のために、31人が同時自爆した)
ただ、それだけだと自爆隊が行ってしまうから、"悪魔の側面"を証言させることも重要だろう。
そして、恐らくオモカゲの計画は、旅団の"慈善活動"を利用してオモカゲもクルタ族狩りに参加し、"眼"だけこっそりもらっていくことだったんでしょうか。
ただ大誤算があって、オモカゲは"人形にしか興味がない"から「緋の眼が自分以外にとってもお宝」ということを知らなかったのではなかろうか。
住民の数(お宝の数)も確認されていたため旅団の眼を欺いて盗むこともできず、変に不和を起こせば入団した目的すら害しかねない上、その場で旅団全員を敵に回すことにもつながり得る。
だから、結局オモカゲは緋の眼を1つも入手できなかった。
村に残されたメッセージは、旅団が報復代行として遺した"シーラの事を指した"メッセージ。
クルタ族抹殺が代行内容だったが、そのついでに本来の自分達の仕事もした、ということだろうか。
虐殺現場を発見したとされる"迷い込んだ"女性もシーラ人形で、わざわざオモカゲが改めてシーラ人形を用いて事件を白日の下に晒したのはまんまと自分の手の上で踊った旅団や流星街、そしてクルタ族の悲劇が可笑しくて、その一部を世間に知らせたかったから―だろうか。
最後にお気に入りの人形を入手した後に、ネタバラシをして全面交戦?
しかし、「蜘蛛のカタは蜘蛛がつける」と大口を叩いた割に、"裏切り者"の相手をまだ"部外者"である、入団希望のヒソカにさせたことにどうも若干に疑問が残る。
ただ、入団志望者が在団員を倒せば交代というルールに、カタをつけさせることによって蜘蛛とみなすとか、団員内で割れてもコインがあるから、アリなのかな。
さて、本題は【原作視点】だ。
まず扱いがやっかいな部分がある。
核心になりうる、例のメッセージ、
"我々は何ものも拒まない だから我々から何も奪うな"である。
というのは、そもそも0巻のQ1の回答によれば、クラピカ追憶編の構想は10巻前後に作られていたが―色々あって―お蔵入りしたらしい。
果たして作者の判断の下「使わない」とされていた部分に、作中の表現との整合性を求めてよいものなのだろうか。
原作において、近年の流星街の住人からの"唯一"のメッセージは、10年程前(クルタ族虐殺事件のさらに5年程前)に起きた同時多発自爆テロでの
"我々は何ものも拒まない だから我々から何も奪うな"
だったとMR兄さん(仮)は言っていた。
裏の世界を取り仕切るマフィア達ですら「旅団=流星街出身」と知ったのはサザンピークでの一件で、世間一般的に流星街と旅団は結びつかない。
しかし、結果的に「クルタ族虐殺事件」の犯人は旅団と断定された様子。
一番怖いのが「映画の販促」だからと言って、元々なかった文言(メッセージ)が追加された可能性。
今風に言うと、"微レ存"?ごめん、言いたかっただけ。
ただあの読切、掲載時の作者コメントによると―

"今はR(レコード)のA面B面に例えてもピンとこないですかね。実はこの読切B面もあるんですが…<義博>"
―B面があるらしいんですよね。
よって、微レ存の想いはありつつも、メッセージがあったのは「正史」で、そのあとのB面で犯行と旅団が結びついた、という前提で進む。
【原作視点】
・旅団に裏切り者はいない
・シーラなる謎の女性が、クルタ村付近まで近づいていた
・クルタ族虐殺事件は起き、メッセージが残された
<情報整理>
・10年前 流星街住民の不当拘束に対する同時自爆テロ発生("拒まない…奪うな")
その際残されたメッセージが、世間一般的に近年で唯一の流星街からのメッセージ(※1)
・5年程前、「クルタ族虐殺事件」発生・発覚("拒まない…奪うな")
・「旅団に流星街出身が居る」というのは一般的に知られてはいない(※2)
・※1と※2から、"拒まない…奪うな"は、流星街の者達だけが使う"文言"ではない可能性
・ウヴォー、パクノダ、フェイタンの反応から、実行犯は旅団と思われる
また「0巻」情報を使って行く。
当初、旅団はクロロの意思によって結成された組織かと思われたが、どうやらクロロから"望んで団長になった"わけではないらしい。
また、クロロはその意に沿わずに決められたことに対して、"決まったことだからがんばる"という人物らしい。
すると、「蜘蛛」なる組織は流星街に元々あった、あるいは以前あった組織で流星街の"議会"によって再結成が決定・団長任命が行われたのかもしれない。
そう思うと、
"ユダは裏切り者ではない"
というのも、「神によって定められた役目を全うした者」として考えれば正にその通りで、どこか自分の境遇を重ねていたのかもしれない。
そしてヒソカによれば旅団は、
主に盗みと殺しでたまに慈善活動もするらしい。
しかしあくまで、ヒソカは途中入団の上、目的は"クロロと闘うこと"に過ぎないので、必要以上に蜘蛛なる組織を探ったりすることもしないだろう。
ただ、ヒソカ視点から見て、得にもならないことをしている様だ。
それは気まぐれの慈善活動なのか、それとも"役目"なのか。
流星街が蟻に襲われた時、
フィンクスらは議会の決定を待たずして、蟻退治に向かった。
それも、
住人の反応からするに、
旅団がたまたま流星街に向かって気まぐれに蟻退治したわけでもなく、住民からしてもそれが意外なことでもないようだ。
つまり、ひょっとすると蜘蛛は「流星街の一機関的役割」を持っているのではなかろうか。
この辺りからそろそろ統合。
ただ、もう1つ検討をぶっこみたいので【原作視点】を1(無難ルート)と2(冒険ルート)に分ける。
まず【原作視点】その1。
クルタ族は"太古の昔からあまたの誤解・偏見・差別・好奇の目にさらされ"、時には"緋の眼狩り"に遭うことすらあった。
しかしながら、定期的に移住を繰り返し人里離れた森の奥地で隠れ住むことにより、百何十年余りの平和をやっとのことで手に入れた。
しかしそこに至るまでの間に、クルタ族は望まない形で争いに巻き込まれた経緯があり流星街の住人と何らかの諍いがあったとするならばどうだろうか。
その時代、爆弾があったかはわからない。ひょっとするとないのかもしれない。
あるいはあったとしても"赤目の悪魔"に報いることができず、そうする内にどこかに消えてしまった、としてみようか。
それから百何十年余りの時を経て、とある女の"発表"、あるいはとある町での"赤目の悪魔"の目撃情報が舞い込む。
"赤目の悪魔"の力は健在のようで、どうやら"こども"が数人の男たちをのしたらしい。
さて、31人同時自爆テロの時は"関係した人間"を殺したが、クルタ族は百何十年余り大きな争いをしていないようだから、下手人はとうの昔に死んでいるだろう。
果たして、その下手人に子孫がいるのかどうか。いるとしたらどう判断するのか。いなかった場合はどうするのか。
そして、流星街の"議会"はどのような結論を出すのか。
流星街の人間は、1人が殺されたから1人が自爆するわけではない。
1人が3年不当に拘束されたことへの報復のために、31人が兵器で命を投げ出し31人の命を奪う、いわば足し算も引き算もない連中である。
すると、「発見したクルタ族の根絶やし」という結論も、あながちありえない答えでもないのかもしれない。
よって、クルタ族虐殺事件の実行犯は幻影旅団で、メッセージは流星街の復讐の意図。
それにも関わらず、あのメッセージが流星街と繋がらなかったのは、「緋の眼」の闇ルートへの流出が原因だろうか。
ヒソカ曰く、クロロは獲物を一通り愛でると全て売り払うそうだが、緋の眼を売ったルートのバイヤーが捕まったのかもしれない。
続いて、【原作視点】その2
私の大好きな"冒険"ルートである。
1と同じく、流星街において、旅団が何らかの機関的役割を持っている、とすることは同様。
そこから検討を加える。
その1では、旅団は流星街の一機関とだけしたが、それではなぜマフィアンコミュニティが取り仕切る地下競売を襲ったのか。
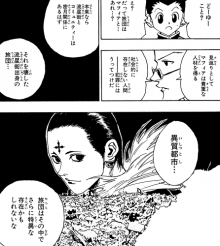
マフィアンコミュニティと流星街は密月関係にある。
もし、旅団が流星街の一機関に過ぎないならば、そんなことはできないのではなかろうか。
ここで別の要素をぶちこんで行く。
クロロの団長就任は自らの意思によるものではなく、何らかの理由で"決められたもの"らしい。
流星街に議会があることを思えば、任命した恐らく議会で良いだろう。
が、地下競売襲撃を考えると、どうも流星街の犬というわけでもない様子。
ひょっとして「第三者」が関わってるのではなかろうか。
そう考えてみると「地下競売襲撃」と「クルタ族虐殺事件」には、とある繋がりがある。
「とある第三者」から見るとそのどちらにも「都合の悪い邪魔者」がいる。
前者は、競売を仕切っているマフィアンコミュニティー、しいてはそれを仕切っている"十老頭"、後者は"クルタ族"それ自体。
思えば、ビヨンド・ネテロは恐ろしいことを言っていた。
ONE PIECEにおける「海軍」と「Dの王国」の関係に近しい読み方になっていくのだが―、

"神話を読み解き遺跡を巡れば太古の昔我々の祖先が大陸から渡来した事は明白"
らしい。
「今、内に住んでいる人々の祖先が外からやってきた」
言うなれば彼らは侵略者であり、元々内の世界にも先住民がいたハズなのだ。
流星街は、
一般常識としては、最初はとある独裁者の人種隔離政策だったらしいのだが、ひょっとすると「元々"内の世界"の先住民が押し込まれた」結果なのではなかろうか。
ただ、中にはそれをよしとせずに流星街以外の内の世界で、ひっそりと暮らす先住民がいるのかもしれない。
【原作視点】の<情報整理>の中で、
"我々は何ものも拒まない だから我々から何も奪うな"
が、流星街の者達だけが使う"文言"ではない可能性と書いたが、流星街に限らず"先住民系"が最終的に採った理念なのかもしれない、ということ。
さて、ここで注目したいのは侵略者と先住民のせめぎ合いがある段階で落ち着きを見せたこと。
恐らく両者間で協議・協定や取引があったのだと思われる。
そして、その時の先住民側の代表組織、あるいは懸け橋、はたまた取引の1つが"幻影旅団"なのではなかろうか。
マフィアンコミュニティにとっても"便利"なように、社会的に存在しない「犯罪にうってつけの人材」こと流星街の住人(先住民)は、社会的に正しくあるべきお偉い方々にとっても極めて使い勝手がよい。
要は、旅団の飼い主は五大国(V5)絡み。
ゾルディック家のような暗殺家業の者と違って金銭も必要なければ、一方的に弱みを握られることもない。
報酬の代価としての「流星街への不可侵条約」また「依頼の範囲内での強奪行為の黙認」。
もちろん黙認とは言っても犯罪行為には変わりはないのでそれが表立てば、法の下に裁かれるのを妨げない。
大分長くなったが、そろそろ統合。
【原作視点】その2
"外"の世界への渡航が管理されているように、"内"の世界においても自由な行動を制限される者達がいる。いわゆる"先住民"である。
基本的には流星街での居住のみを許可しているのが、中にはそれに従わない者達もおり内務省特別管理課(仮)では、そういった民族らの調査・監督・管理を行っている。
ある日、ルクソ地方において"赤目の悪魔"として悪名高いクルタ族が隠れ住んでいるとの情報が入る。
情報を確認するため特別調査員・シーラを派遣。
調査の結果、クルタ族の村を確認。監視体制を敷く。
○月×日、△街にてクルタ族による"異常行動"を確認。至急V5(?)へ報告。
○月×日、クルタ族の駆除と"特別実行部隊"の派遣が決定。
○月×日、クルタ族の駆除を確認。現場に"先住民系"メッセージを加えた上で通報。
○月×日、クルタ族虐殺事件により行方不明となっていた緋の眼の流通が確認され、バイヤーが確保される。バイヤーの供述により、犯行が"先住民系"のA級賞金首、幻影旅団と判明。
改めて"先住民系"の危険性を再確認した上で、新たな"先住民系による被害者"を出さないためにも、目下、先住民系の調査・監督・管理を行ってゆく。
◎クルタ族逆作事件の真相+α まとめ
【映画視点】
犯行は幻影旅団だが、実質は流星街の復讐代行(慈善活動)
しかし、クルタ族に監禁・暴行を受けたとされるシーラという女性はオモカゲの人形で流星街の住民と幻影旅団はまんまと騙されてしまったのだった
【原作視点】その1(無難ルート)
犯行は幻影旅団だが、実質は百何十年余りの時を経た流星街の復讐代行(慈善活動)
シーラは直接的には犯行に関係なし(クルタ族の所在のヒントを晒した可能性あり)。
メッセージが最終的に流星街と結びつかなかったのは、緋の眼の闇ルートへの流出から旅団の犯行が明らかになったため。
【原作視点】その2(冒険ルート)
犯行は幻影旅団だが、依頼主はV5(絡み)。
シーラは内務省特別管理課(仮)に所属する調査員でクルタ族の調査・監視を行っていた。
メッセージが最終的に流星街と結びつかなかったのは、メッセージ自体が"先住民系"が復讐等の時に用いるモノであることと、緋の眼の闇ルートへの流出から旅団の犯行が明らかになったため。
映画の方は内容がアレなだけに正直なんだろうと構わないのだが、原作の方はキレイに繋げたいところ。
新しい武器を入手したら即刻試し切りしたいタイプなので「0巻」情報を元に冒険ルートを突き進めてみたが、如何せんそこは冒険ルート、色々な"危険"を伴うわけです。
まぁ、無難ル―トをもっとキレイに舗装すると大分ニュアンスも変わってくるのかな。
でも、今回はひとまずここで終わり。
以上。
はじめての方へ【再】
はじめまして、ばんぶーと申します。
主にHUNTER×HUNTERの感想を書いておりましたが、休載につきブログも半ばお休み中。
・ハンター好き
・「ストーリー」やら「設定」が好き
・色々考えるのが好き
…そんな人に気に入って頂ければ、これ幸い。
ハンター関連の記事は『H×H感想』タブからご確認頂くとわかりやすいと思うのですが、
今のところ携帯向けに作りかえる予定もないので、
お手数ですが、携帯ユーザーの方は『H×H感想 一覧 』にて、ご確認ください。
以上。
-------------------------------------------
追記:公開日を'12-03-14から、'13-02-09へ変更
ファンブック等の扱いに関して
過去の記事でも、「ハンターズガイド等は、解釈の根拠に使わない」という事はところどころで書いていたんですが、それを書いたのがブログの初期も初期なので、改めてその理由に触れる。
端的に理由を言ってしまうと、ファンブック等の情報は怪しくねーか、ってことです。
ご存じハンターズガイドを始め、ハンタ総集編(Treasure)やリミックス(幽遊白書)など、色々なところで"原作未出"の情報を掲載するものがある。
ハンターズガイドで言えば、念系統など。
ノブナガが"強化系能力者"とされた走りである。
原作を普通に読めば、ノブナガは少なくとも"強化系"ではない。
ハンタ総集編(Treasure)でも同様に、登場キャラクターの―必ずしも作中で明らかになっていない―念系統を明示している。
他になかった情報で言えば、「カストロ=具現化系能力者」ということだろうか。
カストロの念系統は必ずしも明らかにはなってはいないが、ウイングの所見によれば"強化系"である。
作中での"心源流拳法・師範代の説明"とその流れを汲めば、「カストロ=強化系能力者」とするのが妥当ではなかろうか。
リミックス(幽遊白書)では、
(ジャンプリミックス 幽遊白書其之八 魔界の扉編②より)
「ネテロ=強化系能力者」だとか、
精神力、戦闘技術、身体能力、念能力、奇抜さ、知力の6つの要素を5段階で評価した各キャラデータが掲載している。
―さて、簡単にファンブック関連の状況を追ったが、果たしてどのように作っているのか。
ハンターズガイドでは樹想社という編集プロダクションから14人も参加している様なので、その関わりが少ないとも思えないが、部外者(読者)視点ではどの部分を担当しているのか、どの程度参加しているのかは結局のところわからない。
個人的には「作中の描写を元に勝手に補完しちゃってるところ多いんじゃないの」とは思うものの、仮に「編集部から拝借した資料」を元に作っているとしようか。
そこで最大の疑問。その資料はどの段階のものなのか。
1から100まで決めて週刊連載を始める人なんてそうそう居ないわけで―藤巻対談でも触れていたように―普通、一次的に「大まかに決め」、二次的に「(具体的な展開を考えながら)肉付け」する。
幻影旅団という敵キャラを大まかに考えた時のノブナガは、「幻影旅団の特攻隊員」程度にしか決められておらず、「特攻隊員=強化系(仮)」程度のものだったのではなかろうか。
つまり、もしハンターズガイド等が「編集部から拝借した資料」を元に作られているとしても、そのデータは相当初期の物のように思われる。
作中描写(=作者の検討の結果)から言えば、ノブナガは明らかに強化系能力者ではないからだ。
続いて、リミックスで掲載されているようなデータ(数値)関連。
データ(数値)というと、それだけで客観的なものに感じてしまうが必ずしもそうではない。
どのように算出したのか、何を基にしているのか、それが大切であって何の検討もなしにその数値を信用できるハズもない。
そもそも作者の検討(肉付け)前の大枠の設定にしても、あまりに抽象的過ぎる上、色々おかしい。
特に違和感を覚えたのが"奇抜さ"だ。
何をもって測っているのかイマイチわからないのだが、ピトーやプフやコムギが5(MAX)で、ユピーが4。メレオロンが3なのだとか。
検討前の大枠の段階でも王や護衛軍は性質上「飛び抜けて強い」と位置づけられる。
そして、討伐隊(ハンター達)は純粋な意味での力では及ばないからこそ"上手く"戦う必要があり、その1つとしてメレオロンの「奇抜さ」が鍵になっていたのではないのか。なぜ、そのメレオロンの「奇抜さ」が3なのか。
また、コムギの奇抜さが5とはこれ如何に。知力が5ではないのか。
コムギが軍儀以外では何もできないから、「奇抜さ」に振ったのだろうか。
しかしその発想ならば、それこそメレオロンの奇抜さ3はおかしいだろうに。
加えて、仮にリミックスのステータスの全てを全面的に正しいとしても、全体的に劣っているゴンは全力のピトーに結果的に勝利した。
つまりは、能力や制約と誓約次第ではひっくり返る、要は念での闘いが揺蕩っているという原作主義に立ち戻るわけで、このステータス表自体なんら意味を持つ様に思えないのだ。
ファンブック等の情報を「全て正しい」とすればおかしい部分は出てきてしまうし、自分の解釈に「都合のいいところだけ根拠に使う」というのも個人的に好ましくない。
―そんな理由で当ブログでは、ファンブック等の"原作において未出の情報"は"怪しいから使わない"というスタンスを採っています。
(「ファンブック等」と適当に括ってますが、"原作"以外を包括的に指しており、アニメも含んでいます)
ただ暫定的な例外を2つ想定している。
1つ目が、作者から出た情報。
ワンピなら「SBS(質問を募集するのだ)」、ハンタなら0巻での「一問一答」、トリコなら「動物&食材リスト」…など。
"原作"の情報と言うとちょっと違うのだが、一応の"正式解答"であるため使用可としている。
ジャンプフェスタなど、ファンを目の前した"生の発言"もそれに含めてよいと思われるが、(作者自身の)十分な検討を経ていないリップサービスの可能性もあるだろうから―考える時間的余裕が存在する―単行本収録情報にはやや劣るか、とは思っている。
2つ目が、原作で明らかになっていないキャラの名前。
ハンタで言えば、ゾルディック家の高祖父(=マハ←ハンターズガイドより)とか、クラピカの師匠(=ミズケン←アニメより)など。
こちらは単純にそのキャラの話をする時に不便であるため。
しかしながら、あくまで漫画家さんは「"漫画で"表現する方」なので、この2つの例外も"原作"で情報が更新されれば(特に既存情報と反する場合)"原作"情報を優先する。
―ちなみに「ファンブック等の情報を使ったらダメ」というわけではなく、単純に「使う前提の人」と「使わない前提の人」は話がうまく噛み合わない、ということです。
とまぁ次の記事に関連して、今後ありうる"反発"への"お断り"記事でした。
以上。
H×H 蟻編 アニメ化決定 + ジャンプVS
◆蟻編 アニメ化決定!(4/21~)

ゴンとカイトの出会いが省かれていた事や、蟻編のグロ描写等から新アニメはG.I.編で終わりかと思っていたのだが、どうやら蟻編も新アニメでやってしまうらしい。
"大好評"の映画やアニメの視聴率、またそれに伴う物販の動きやら諸々を受けて、恐らく"あとから決まった事"なのだろうが、いやーびっくり。
私はあくまで原作ファンなのでそこまでアニメに興味はなかったんですが、"どこまで描かれるのか"はすごく気になる…というか王や護衛軍が"動く"のは正直ちょっと見たいなぁw
また、蟻編やるってことは―さすがにゴンさん瀕死状態で終われないだろうし―アルカ編(?)までやるんでしょうかね?
映画第2弾でネテロが出てくることを思えば、蟻編の終わり方自体変わってくるのだろうか…?
大して見てもいない私が新アニメを語ろうなんておこがましいのだろうが、どうも監督もしくは制作陣にショタコンor腐女子属性を持っている方がいるようで、一見した印象としては鼻につく感じがした。
しかし、蟻編ではある時期からソレが、激減orなくならざるを得ないだろう。
元より念描写に関しては何の期待もしていないので、アレさえなくなれば大分見れるようになるんじゃないか、と若干思ったのだが―

―やっぱ色々違うよね…(苦笑)
この幼いキルアで、あの"苦悩"は上手く描けるのだろうか。ちょっと心配。
まぁ…本誌再開もしばらくないだろうし、お茶を濁しましょうかね。
濁り過ぎて何だかよくわからないものになりそうだけど、「それはそれ」として緩く…ね。
―そう言えば、余談だけれども。
テレビで「テルマエ・ロマエ」の作者であるヤマザキマリさんが「映画化までの流れ」を暴露していたらしい。
それによれば、使用許可とかその額について作者の意向はお構いなしに「勝手に原作使用料を100万円」で売られていたんですってね。
("彼の"秀峰兄さんですら映画2作目で250万だったらしい(今は交渉して売り上げに応じてもらっている様子))
原稿で忙しい中、番宣に駆り出され丸一日拘束されても出演料はゼロ。
もちろん映画公開でコミックスは増刷されるから、何のプラスもないわけではないんでしょうけど、作者からすればそれ以上のマイナスがあるかもしれないわけで。
なんか最近、漫画等原作の作品が増えてる印象があったんですが、こうゆう理由なんでしょうね。
多少幅はあるんでしょうけど、"たかだか100万"程度なんですから、そりゃおいしいですわ。
漫画業界は、昔に比べ漫画家さんの権利が向上しているように思っていたのですが、そうでもないんですな。
それとも"あの業界"が893過ぎるのかな。
冨樫さんが0巻で「意に沿わずに決定されたら、無視するか、ふてくされてダレる」なんておっしゃてましたが―、あの映画もやっぱり"そうゆうこと"なんでしょうなぁ。
何も言えねェ。
13号情報ついでなんですが、来月発売(3/22)予定のジャンプの新増刊「ジャンプVS」について。
情報出尽くしたわけでもないので、ひょっとすると間違っている部分もあるかも知れないが「バトル」をテーマにした特別増刊号で、位置付け的に新人系の「ジャンプNEXT(旧赤マルジャンプ)」と「週刊少年ジャンプ」の『間』くらいの様に思われる。
恐らく、連載会議にかけられた(or乗りかかった)新人漫画家さんを集めて「バトル漫画」を描いてもらうって感じなんでしょうが、この増刊号で読者から高い評価を受けた作品は連載行く可能性高そうですねぇ~。
それにしても新人系とは言え面子が結構豪華ですね~。
(※原作・作画と分業している場合は作画担当を優先表記・敬称略・50音順、リンク付=無料公開、☆=個人的に好印象、"┗"=過去作品)
◆天野洋一・成田良悟…『ステルス交境曲(-シンフォニー)』
┣(天野)「OVER TIME」(☆)、「AKABOSHI」ほか
┗(成田)「デュラララ!!」、「BLEACH Spirits Are Forever With You(J-BOOKS)」ほか
◆石山諒…『パラサイトB』
┗「デコ・ボコモンスター 」、「ユミルの魔人」(NEXT'12-春)
◆岩本直樹…『ここだけの秘密』
┗「magico」ほか
◆大須賀玄…『怪物監獄』
┗「ケイドロ」(赤マル'09-春)(☆)、「GHOSTRONG」
◆久幾田文章…『除霊戦士 北枕くん』
┗データなし
◆芝田優作…『ヨアケモノ』
┗「ARMORED」(赤マル'09-夏)(☆)、「明治百機八匣譚 DENGI」(WJ'09-35金未来)、「ENAM GAVEL」(WJ'11-9)
◆すがぬまたつや…『疾風のなかよし』
┗「愛嬌の沼」(第76回赤塚賞・佳作)
◆三浦悟…『かちぐみ!』
┗「なまくらShraPnel」関連(トレジャー賞 )(赤マル09-夏)(NEXT'11-夏)、「瞬間×ヒロイズム」(WJ'10-35)
◆三木有…『改造人間ロギィ』
┗「改造人間ロギィ」(WJ'11-8)(☆)、「呪禁奇譚」(WJ'12-47)(☆)
◆ミヨカワ将・古橋秀之…『EGG KNOCKER(エッグノッカー)』
┣(ミヨカワ)「有料戦士 ペイソルジャー」(RE'06)(☆)、「ガラアクタ」(赤マル07春)(☆)、「FOO FIGHTER FUJI」(赤マル08春)(☆)、「血風学級怪」(WJ'09-21)(☆)、「ST&RS」
┗(古橋)「ブラックロッド」、「ある日、爆弾がおちてきて」ほか
◆屋宜知宏(やちともひろ)…『アイアンナイト』
┗「ゴブリンナイト」(WJ'12-35)
◇おまけ
『小畑健描き下ろしポスター』
『天野洋一描き下ろしポスター』
『大石浩二特別漫画(詳細不明)』
『岸本斉史・島袋光年対談』
『謎企画』
まだ発売まで1ヵ月ありますが楽しみれす。
以上。
ジャンプBOOKストア!PC版
最近、少しずつではあるが確実に電子書籍の世界が動いてきている。
個人的には週刊少年ジャンプ絡みで拡充してくれたら、もうそれだけでいいんだけど、最近ちょっと嬉しいことがあった。
「ジャンプBOOKストア!」がPCと同期できるようになったんですよ。
(スマホ等でジャンプBOOKSストアにて購入した電子書籍がPCでも読めるようになった)
「今までそんなこともできんかったんかい」
って感じなんだけど、はい、やっとできるようになったみたいです。
HP でアカウント作って(スマホのアプリ上でも作れるけど)、
PCからログインして、スマホのアプリ上からもログインして、
PCからHP の本棚クリックすると
同期されて、購入済の本棚を表示できる
って感じです。
(筆者がやり方わからなくて、若干時間食ったので説明おいときました)
まだまだ使いにくいし、重いし発展途上なのは目に見えてわかるんだけど、この数年で本当に大きく前進しましたねぇ。
この勢いで、ジャンプ本誌を発売日当日に購入できるようになったら嬉しいな。
そうゆう意味では週刊モーニングは冒険というか、探求心ありますよねー。
月額500円で、発売日に読める定期購読があるらしい(雑誌が定価330円ほど)。
まぁ、バガボンドとBILLY BATに関しては両作者が「紙媒体で見てもらうように作っている」という拘りがあるため電子書籍版には入っていないという難があるんですけどね(笑)
さてそんなわけで、より電子書籍のサービスが向上してほしいとは思うものの、やはり需要が伸びて行かないと難しいわけでして、微力ながら2つほど電子書籍でご紹介。
1つ目。
ジャンプ関連でも、ジャンプBOOKSストア絡みでもないんだけど、
こうゆう電子書籍になれていない方でアイフォーンとか持ってる方は、試しに「iBooks(無料アプリ)」をダウンロードして、秀峰兄さんの「ブラックジャンプによろしく(全13巻無料)」とか読んでみると、大分慣れ親しめるんじゃなかろうか(対象年齢は15歳以上かも?)。
全ての見開きではないんだけど、ノド(ページとページのつなぎ目)もきれいに繋いであるし、電子書籍の良さも感じられるかもしれない。
(※ちなみに、残念ながらジャンプBOOKストアの電子書籍はビューアーの仕様上、ノドは分断されている)
2つ目。
こちらはちゃんとジャンプ関連の、ジャンプBOOKSストア絡み。
実は、ジャンプ電子書籍には「オールカラー版」なんてものがあるんですよ。
既存のモノクロのコミックに着色がしてあるんですが、これが結構新鮮かも。
ちなみに、先々週の33号の45周年記念号のデジタル版(紙媒体と同時発売)では、ワンピ、ナルト、黒子、暗殺の4作品のみだが、モノクロ版に加え、カラー版も同梱されていたりする。
「硬派系のオタク」(笑)としては、
誰がその配色決めてるの?
まさか、作者にこれまでの全ての色の指定を聞いてるわけじゃああるまいし、勝手に色決めちゃって塗って売ってるの?それってどうなん?
とか言いたくなるところもあるんだけども(この勝手な指定で、そのキャラ等の配色が一般化するのが嫌)、そうゆうのを気にしない方なら、楽しめるかも。
通常版(モノクロ版)に比べると100円ほどお高くなっている様だけど、無料で立ち読みはできるようになっているので、気になる作品でオールカラー版があれば試してみるのもいいかもしれない。
わかりやすく特定層に向けて発信するなら、To LOVEるのカラー版とか結構好きかもねって話。
まぁ、児○ポ○ノ規制絡みで、そう遠くない未来消えるかもしれんけど。
―そんな感じでステマっぽいけど、とあるメッセージを目的とした記事でした。おわりんこ。
色んな事情で詳しくは言えないけど、スマホ版PC版ともにビューアーの仕様は変えたほうがいいと思われる。今の仕様は、好ましくないことが簡単に出来てしまう。
もちろん後から法的に叩きのめすこともできるだろうけど、それは実質的にあまりにナンセンスじゃないかね。
【劇場版】HUNTER×HUNTER【第2弾】

劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
2013年12月27日(金)公開
------------------------------------------------------------
監督:川口敬一郎
脚本:岸間信明
アニメ制作:マッドハウス
<あらすじ>
かつてハンター協会に存在した最強のハンターたち。
彼らは≪光≫と≪闇≫に引き裂かれ、それぞれの道へと進んだ。
そして、全ハンターを抹殺するために≪闇≫が動き始める!
ネテロとハンター協会の罪深き真実が判明し、すべてを知ったゴンがとった行動とは…!?
------------------------------------------------------------
ゴンとキルア、なんでそんなにエラ張ってるの?
という疑問はさておき、あらすじの時点で何かすごいことになってそうで怖い。
察するに、清凛隊が誰ぞやの謀略により―“任務”の名の下―表舞台に立つ者と、裏で暗躍する者に分けられ、ハンター協会(?)の秩序保っていた。
が、何かをきっかけに想いが爆発して、事件が起きるっていう感じの導入なんでしょーか(適当)。
それにしても、今回は時系列的にどこなんだろう。
蟻編後だとすると、ゴンさん化→治療→ゴン・キル離れ離れに、という流れが出来てしまうから難しいよなぁ。
いや、エンディング自体変えてくるかもしれないし、
変えてこなかったにしても“何かあったらすぐ連絡してよ”の言葉通り、呼び戻せばいいから、なくはないか。
それともこのワンシーンとって、
ちょんまげある=蟻編前?
いや、この画像は「事の発端」=回想で採れば、別に蟻編後の話でもおかしくはないか。
でも副題の「ザ・ラストミッション」で考えると、蟻編前は厳しいのか。
「ラストミッション」後に「蟻討伐ミッション」になってしまうもんね。
蟻編後のラストミッションで考えると―、
「ネテロのラストミッション」なら、蟻編のエンディング自体変わっちゃってるよね。
しかし、あの状況下で薔薇のような方法以外でネテロがメルエムを倒せるとも思えない。
さすがに蟻編のエンディングは変えてこないだろう。
では、蟻編後=ネテロ死亡後の「ネテロからのラストミッション」になるのだろうか。
ただそれだと、遺言DVDどうなるんだろ。
あれ(選挙この条件で)やって、これ(今回の映画の内容)やって、って言ってるのにその内の1つをラストっていうのも違和感あるよね。
闇=裏で暗躍するように言われた者(?)から見て、「ネテロからの最後かつ最期のミッション」でラストミッション?
“ネテロからのミッションだからこそ「義」で果たしていた”
みたいな理由があるなら蟻編後=ネテロ死亡後は、その理由がなくなり、裏から表に姿を現してきたっていう流れには繋がりやすいだろうか。
あるいは、そいつが起こす今回の騒動自体が、与えられた任務の〆にあたるってことかね。
どうもそのあたりが無難な気がする。
それにしても、ネテロの後ろにある天空闘技場が舞台っぽいんだけども…どう関係してくるんですかねぇ…w
まだ情報もちょっとしか出て来てないし、冨樫さんの手が入ってる感じもしないので、変に考えるだけ後で虚しいだけかねぇ…。
まぁ何にしても、どんな内容であれ、来場者特典でまた何かついてくるなら…結局見に行ってしまうんですけどね…。。。
NARUTO 646話 感想
ツイッターの方で書こうと思ったんですが、元々入力できる文字数が少ない上、画像挟もうとすると絶望的状況になるため、こっちで書こうと思う。
お題は今週のNARUTOの話と言いましょうか、厨二の星「写輪眼」関連のお話。
輪廻眼って、

本当の形はこれじゃなくて、
これなんじゃね、みたいな話 を3年くらい前(月日の流れに驚愕)に書いてたんですが、終盤に近づきようやくお答えを頂戴できそうなのだ。
まず、肝心の輪廻眼だが
マダラがオビトに説明していた十尾の眼に写る天印(まがたま模様)の数が少なかったのだ。
回想での描写というか設定が変わってしまったのだろうか
あるいは、まだ完全に設定が固まってなかったのだろうか
等と不安に思うところもあったのだが、今週の646話にて、
それも、マダラがやった時の想像図としての形である。
オビトが輪廻転生の術をしなくとも、十尾の人柱化しても、今まさに無限月読を行おうとしても、
マダラが余裕を見せ、今なお「それ(無限月読)を為すのは…このオレだ」と言い放てるのは、この描写のズレこそが理由で、力不足(?)で失敗、もしくは“強力な術”の返しを受けることを示唆してるんですかねー。
伏線が回収されそうな予感にワクワクしてしまうんですが、今週のものは3年越しの回答だけあっていつも以上に気持ちが高まる。
まぁ、輪廻眼の天印の数が足りないのはオビトのレベル不足なのか、“部品”不足が原因かなのかはまだ何もわかってはいないんですけどね。
―と、気持ちよく来週を待ちたいところなのだが、しかし。
改めて今週号読み返すと不穏なものが最初の1コマ目にあるではないか。
わかりますかね…。

何故か、3つ目の輪にも天印出てるんですよね…。
設定を思い出し―これまで書いてなかったものを―あわてて書き足したのか。
アシスタントさんが、早合点して書いてしまったのか。
それとも天印っぽく見えるだけてインクのシミとか、印刷過程でのヨゴレなのか。
3つ目の輪に現れる天印にしても場所が違うので、ミスっぽい気もするんですが…、エロ仙人のダイイングメッセージのように自分が想像していた伏線回収とは全く違う方向性を出してくることもあるのでちょっと怖い^q^
そんな感じでwktkとgkbrを合わせたような不思議な気持ちを抱いた回でござんした。
以上。
【H×H映画】もうがまんできないっ【第二弾・続報】
ある段階から、イジったらアカン奴やと思ってはいたのですが…もう我慢できないっ^q^ (イジらずにはいられない)

12/27公開予定のH×H映画第二弾「The LAST MISSION」ですが、少しずつですがその内容が明らかになって参りました。
<あらすじ>
天空闘技場で開催される戦いの祭典「バトルオリンピア」を訪れたゴンたち。
だが、いよいよ祭典が開幕するというその時、武装集団が闘技場を襲撃!闘技場最上階にいたネテロを「念」とは違うオーラで捕らえ磔(はりつけ)にしてしまう!
彼らの正体は、ハンター協会の 《影》 だった…。
「影」とは、かつてハンター協会に所属していた集団で、協会の闇の部分を背負わされていたが死んだとされていた様子。

彼らは念とは対極の、“怨”という禁断の力を用いる様だが、それを“生前”から用いていたのか、“死”んでからその力に目覚めたのかは不明。
念能力がオーラ(生命エネルギー)を自在に操る力なのだから、その対極の力である怨能力は死者(の残した?)エネルギーを自在に操る力のようなものだろうか。
その印象からすると、影たちが怨能力に目覚めた(?)のは臨死体験(?)後のような気もするのだが、はてさて。
とりあえずわからないことだらけなのだが、
絵だけで判断すると怨能力を使用している最中は目の色が変わるっぽい。
すると、「影」の内、怨能力が使えるのは左の二人(ジェド・煉獄)だけなのだろうか。
しかし、文で判断すると煉獄のキャラ説明には―
“自らの命を犠牲にするほどの制約と誓約で手に入れた最凶の「怨」能力者”
―とあり、
ジェドが自らの命を犠牲するほどの制約と誓約で、煉獄という「怨」能力者を手中に収めたのか
煉獄自身が自らの命を犠牲するほどの制約と誓約で、最凶の「怨」能力を手に入れたのか
よくわからない。
まぁ、センリツのキャラ説明で
クラピカと同じスーツ姿ということは、同じ職場かも!?
なんてとんちんかんな事を書いているので、あまり書いていることを鵜呑みにすべきではないのかね。
ジェドという名のボスらしきおっさんは、ネテロと対等に渡り合うほどの力を持つ伝説のハンターとされているが、ネテロをあっさり(?)捕えるってことはメルエムより強い設定なんですかね?(苦笑)

ポスターでのネテロの表情からすると、自らの罪に対する罰として受け入れたってことなのだろうか。
しかし、そうだとしても個人的に襲撃してきたのではなく、わざわざバトルオリンピア中に襲撃してきたということは、自分を殺すことだけが目的ではないのだろう。
すると、そこで自分だけあっさりと敵の謎の攻撃受ける(結果捕まる)っていうのもなんだかねぇ。
メルエム戦において、
"俺は一人じゃねェ…"
と、個人的なわがままと、ハンターたる責務を明確に分けていたネテロの姿勢としてはジェドの攻撃を受け入れたっていうのも違う気がするんだけどなぁ。
◆時系列
ポスターで、ゴン&キルアが発を用いていることから、GI編と蟻編の間かと思われる
◆怨能力
映画第一弾感想で、制作陣はそもそも念能力を理解する気があるのか云々書いたが、そんな気持ちはなかったようだ!
と否定的に取りそうになるが、そうだよね、見る前からよくないよね。
アルカ(ナニカ)の力を、「念ではない力」と採ったんだよね。
うんうん、作中で「念能力である」とも明言してないもんね。
学生時代によくいた、ほんの一部を理解したことで全部を理解したつもりになって「極めた」とか軽々しく口にする輩や、
うまく理解できないことへの言い訳というべきか反射というべきか、「飽きた」という隠れ蓑を使って次の要素へすぐ手を出そうとする姿勢を思い出してしまって、どうも私は否定的に感じてしまうのだが、前回の映画の様子から変に念を描写させるよりは、そうだね、ライト層やお子様方には見やすいというか、わかりやすいかもしれないね。
何気にハンタが連載(と言えるかわからんが)15周年目らしいので、さすがにそろそろ連載再開かな、とか思っていたけども―
"自分の意に沿わずに決定された"場合、"無視するか、ふてくされてダレる"らしいので、こりゃまだしばらくないのかねぇ。
FF14?が出たらしいし。
◆映画入場者特典
今回の特典は
有名な書道家先生使うのもいいとは思うんですが、
「名前■(はんこ)」
とか、入れるんだったら微妙じゃねぇかな。
ハンターに関係ないですし。
それなら単に書道に通じた無名の人でよかったなぁ。
ちなみに左の心Tシャツは、前売り券についている応募券を出して、抽選で当たるものなのでご注意をば。
まぁ、何にせよ今回は「0巻」のようなものではなくて安心でござった。
以上。
ハンタ映画の第1弾が地上波初登場!
【未視聴者 注意】The LAST MISSION 感想【H×H映画第2弾】
一昨日公開のHUNTER×HUNTER映画の第2弾、『The LAST MISSION』早速見て参りました~。
一応初めに言っておくと、今作もオリジナルストーリーのパラレルです。
(強いて言うならNo.186とNo.187の間のパラレルかな)
第一弾(緋色の幻影(ファントムルージュ))の時は、
やれ冨樫さんが制作に関わっているんじゃないか(面白いんじゃないか)
やれクルタ族惨殺の真相が明らかになるんじゃないか
やれヒソカの前の旅団メンバーが描かれることで、(作中の進行状況的に)回収されていない伏線が拾われるんじゃないか
と、色々な期待を寄せていたので見に行って本当に落胆してしまったのですが今回は、
冨樫さんは関わってない
何やら「怨」なる、念能力の対極の力を創出している
ネテロはろくに抵抗も出来ずに捕まるらしい
と、見る前からアカン空気を醸し出してくれていたので、安心して見に行けた。
見に行った率直な感想としては第1弾よりは大分マシ、と言ったところ。
相当ハードルを下げて見に行ったのも大きな要因ですが、(脚本の岸間さん曰く)制作サイドからゴンとキルアをベッタリな話にはしない要望があったことも幸いしてか、脊髄反射的に嫌悪感を抱くようなシーンが激減した事が大きい。
ただ、全体的に設定がふわっふわっしていたかな…(笑)
まぁ、追々その話にも触れていくつもりですが、まだご覧になって居ない方には…正直そこまで見に行くのはお勧めはできない。
“ハンタの同人が映画化した”くらいの感じで「キャラを見に行きたい」という気持ちならいいかもしれない。
参考までにキャラの活躍具合。
ゴン…概ねの念を習得済 一番頑張る
キルア…概ねの念を習得済 二番目に頑張る
クラピカ…概ねの念を習得済 三番目くらいに頑張る
レオリオ…纏を習得済 お得意のナイフや励ましで頑張る お笑い要員
ヒソカ…遠くから上記4キャラを見守るキャラ 相変わらずそのお力は披露せず(脚本の1稿、2稿目では活躍シーンがあったようだがカットされたらしい)
ネテロ…基本はりつけ状態だが、アニメではまだ見せていない百式観音を一足お先にお披露目(個人的に百式観音の頭上で祈りを捧げる小さな観音様の造形に不満)
ズシ…いつまにやら天空闘技場のフロアマスターに ボコられ役+α
ウイング…描写外で戦闘有
ビスケ…ゴリラ化せずに、若干戦闘あり
ゴレイヌ…えげつねぇ男の色気をガウンで醸し出す チラ出
パリストン…ご尊顔のみ2度チラ出 声も出さず
ビーンズ…ナメック星人バリの顔色の悪さに驚愕
ジェド…大ボス 白髪のお兄さん 終始登場 声は中村獅童さん
修羅…黒髪ロン毛のお兄さん 概ね登場 声は天野ひろゆきさん
餓鬼…ゴリラお兄さん そこそこ活躍はするものの声に芸能人が起用されていないため各所での紹介が薄い
煉獄…小柄な少女 出オチ 声はCamCamの専属モデル・山本美月さん
※私の後方に居た、小説もしっかり読んできたと息巻くお姉さん曰く修羅・餓鬼・煉獄の3キャラには深い設定があるのらしいのだが映画内では全く活用できておらず、そこそこプンプン丸だった。
それではそろそろまだご覧になっていない方には例の如く「アレ」になるのでこれ以降はスクロールにご注意をば。
◇もくじ
・ストーリー
・怨とは
・敵の怨とその“せいやく”
・題目の意味
・感想
◆ストーリー
半世紀以上前の事、ネテロにはジェドという名のライバルが居た。
二人は今のゴンやキルア達の様に切磋琢磨し合っていた。
そんなある日のこと、ひょんなことからジェドは自らの意思でハンター協会の闇を担うこと、そしてネテロには光を担うよう告げ、二人は袂を分かつこととなった。
ネテロは「清凜隊」を率いて八面六臂の活躍をする一方、ジェドは暗殺や破壊工作といった裏ミッションを担う「影」を率いた。
しかし時代は移り変わり、秘密を知り過ぎた「影」達はむしろ邪魔になったのか、彼らは危険視されるようになったのだった。
それにも関わらず「影」達の活動は一層過激化し、ついにはネテロに「ジェドをハントせよ」との指令が下る。
(この時点でジェドは右の発を使っていなかったかも?忘れた)
本来、ハンターはハンターを標的にできない。できるとすれば例外規定にあたる場合である。
※ハンター十ヶ条
ハンターたる者 同胞のハンターを標的にしてはいけない
但し甚だ悪質な犯罪行為に及んだ者に於いてはその限りではない
ジェドは自分を裏切ったハンター協会やネテロに強い恨み膨らませ「怨」に目覚め(?)復讐を誓うも、ネテロの百式観音の前に敗れ去った。これが数十年前のことである。
多くの「影」達はその戦乱で命を落としたが、わずかに生き残った者達も、“秘密を隠し通したい大人達”の罠にかかり収容所にてその人生の幕を閉じた。
どうにかしてそれを逃れた修羅、餓鬼、煉獄兄妹だったが、
言われなき迫害や生涯身を隠さねばならないことに復讐心を募らせた。
そして、そんな彼らのハンターへの復讐心(怨念)が、ジェドをこの世に蘇らせることとなる。
蘇ったジェドの目的は、隠された「影」達の歴史を刻んだブラックレコードを世に公表すること。
そして、すべてのハンターを抹殺すること。
―ハンター協会の闇を知ったゴン達は何を想い、どう彼らと向き合うのか。
…みたいな話だった気がする。
◆怨とは
今作品を語るにはまずはこれになるのでしょう。
「怨」って何よって話。
怨とは―念能力の対極にあり、怒りや憎悪を源とする力。
念よりも強大な力を得ることができるが、とても厳しい“制約と誓約”を結ばなければならず、命を落とす者が後を絶たなかった。そのためはるか昔に封印された禁断の能力。
◎怨の特徴
・怨を習得すると念が使えなくなる
・怨で気配を消すと、円でも感知できない
・怨に目覚めると“せいやく”を結ばないと死ぬ
・念と違い六相図で示された様な得手不得手がなく、全系統の能力が自系統の様に使用できる
◇念の対極
当初、念能力がオーラ(生命エネルギー)を自在に操る力なのだから、その対極の力である怨能力は死者(の残した?)エネルギーを自在に操る力のようなものだろうかと思っていたのだが、怒りや憎悪を源とする力とのこと。
歓喜、狂気、悲哀、恐怖、憎悪、油断、忠義、激昂、疑心、愉悦、羞恥、覚悟
ありとあらゆる心の動きが作用して念を加減するものなので、怨の言うところの怒りや憎悪を源とするの意味がよくわからない。
念の対極に位置するというよりも、念の中でも強力だがひどく不安定で歪な極地、という表現の方が近い気がする―が、どうしても制作サイドは念とは対極に置きたいらしい。
そしてそのスタンスに乗っかるなら、念は愛やら慈しみを源とするのかと思ったら、本当に百式観音は慈愛の心を源とするらしい。
百歩譲って、百式観音は感謝の正拳突きの精神が根本にあろうからわからなくもないのだが、クラピカの蜘蛛特化の念や、犯罪に走る念能力者の念の源ってなんなのでしょうかね。
◇その他念の特徴
・円で察知できない
BLEACHでいうところの、崩玉を取り込んだ愛染のように別次元の存在になったから感知できないとかそうゆう類なんですかね。
その理論(?)で霊圧、もといオーラの様子が察知できないのはいいにしても、ネテロは自身に近づく怨能力者の存在に気付いていた。
特段円をしている様子もなかったんですが、どうやって気づいたんでしょ。
気配や音なんですかね。
オーラが察知できなかったとしても何かよくわからん奴が自分に近づいていることくらいは察知できると思うんですがどうなんでっしゃろ。
・六相図の概念がない
全てが自系統になる、というべきなのか
クラピカの「絶対時間(エンペラータイム)」は簡単に言えば
どの系統の能力も100%引き出せるものだが、正確に言えば
“覚えた能力であれば”いかなる系統のものでも100%の精度・威力で使用できるというもの。
怨はどっちなんでしょうね。そのあたりの言及はありませんでしたが、怨をとにかく持ち上げる流れがあったので全系統100%使えるっていうノリなんでしょうか。
しかし第1弾と同じで、強化系の強力な攻撃を防ぐ力があるかと思えば、レオリオの纏は突き破れない攻撃力。なんでや。
・怨を覚えると念を使えない
ジェドの血が体内に入ると怨に目覚めるんですが、何故か念が使えなくなる。
しかし、いざ怨を習得すると使っているのは結局のところ念の時と同じ技(発)なのだ。
何がどう違うのか、全くわからない。とりあえずは威力は上がってる様だった。
・せいやく
“せいやく”、つまりは「制約と誓約」なのだが、どうも意味が違うように思われた。
原作では制約(ル―ル)を誓約する(守ると誓う)ことを指すが、
映画では自分との約束というよりも、「ジェドに忠誠を誓う」というものに思われた。
映画内で誰かさんが怨に手を出すのだが、怨は“せいやく”しないと死ぬため、誰かさんは“せいやく”をすることになるのだが、
せいやくっ!!!
という姿には思わず笑ってしまった。
◆敵の怨とその“せいやく”
映画内でその内容を言っている者も居たが、中には言っていない者も居たため、パンフレットの情報を元に一部補完。
◇ジェド
血を与えることで、相手を怨能力に目覚めさせる
通常注射器のようなもので血を抽入するが、出血を浴びせることでも有効
・百鬼呪怨・羅刹(ひゃっきじゅおん・らせつ)
ネテロの百式観音の影響をモロに受けたかのような能力。
能面のような顔をした具現物(?)。
フォルムとしては、ドラクエ6のラスボス・デスタムーア(第三形態)がマントを羽織っているような感じ。
手が伸びたり、口からレーザー飛ばしたり、手からレーザーを出したりする。
・“せいやく”
制約:血の忠誠から、憎きネテロを除外すること(ネテロに効かない)
誓約:復讐心が薄れると命も肉体も失い、血の忠誠によって従えた者たちが解放されてしまう
◇修羅
・機械に巣食う棘(マシンイーター)
機械を意のままに操ることが出来る
・物真似鳥(シェイプシフター)
相対する敵を完全にコピーし具現化することができる能力
相手を構築する際に、その者の情報(記憶)を知ることができる
またコピーした人形は怨に目覚めた状態のため(全系統100%)、相対する者よりも強い人形が作れる。
平たく言えば、映画第1弾のオモカゲのソウルドールの上位互換。
・“せいやく”
制約:不明 (ジェドに終生の忠誠を誓う?)
誓約:貞操を守らければ死ぬ(パンフのみの情報)
◇餓鬼
・踊る気儘な火人形(ダンシングドール)
人魂のような複数の念弾を自由自在に操る
・“せいやく”
制約:不明 (ジェドに終生の忠誠を誓う?)
誓約:ハンターに負けを自認すると自爆する
◇煉獄
・漆黒の処刑台(オンバサラ)
念能力を封じ込めた上で、相手を磔(はりつけ)にする能力
拘束された対象に触れようとした者を自動で攻撃することもできる
対象から50歩以内に近づいた状態で自ら命を絶つことで発動
・“せいやく”
制約:ネテロのみに使用する
誓約:不明
ただ、ここでも疑問が。
修羅の「貞操を守らければ死ぬ」という“せいやく”は、煉獄のものなのではなかろうか。(作中では一切の言及がなく、パンフレットのみの情報)
漆黒の処刑台の不可侵性は、純潔を守っているが故の神聖さ(?)とも精神的にリンクできるように思われる。
男の修羅が「ヤったら死ぬ!これ“せいやく”だかんね!」というのは、まるで極度の女好きで、女性とその様な関係を持てないことへの鬱憤や悲しみを増幅させ、怨の力を強めているかのようなおかしさを連想してしまうのだが、どうなんですかね。
◆題目の意味
「The LAST MISSION」とあるが、どのような意味だったのかイマイチわかりかねてしまった。
最後に、ネテロがジェドに対してもう恨んではいないのではないか、他の者達の怨念を果たそうとしているだけではないのか、みたいなことを言っていたと思うのだが、今回の事件はジェドの最後の使命ということだったのだろうか。
元々ジェドは「影」として、表立って出来ない任務(裏ミッション)として、各種の破壊活動や暗殺を行っていた。
個人の考えとしてはそれが正しい解決方法ではないと思っていても、任務という名の大義名分の下こなしていたのだろう。
今回の事件は、天空闘技場で行われたバトルオリンピアを襲撃し、
ネテロという生ける伝説を捕えることで自分達の武力を示し、
観客(明確に描かれていなかったが、政府絡みのお偉方も居たのだろう)を人質にとった上で「影」達の“歴史”が示されたブラックレコードの公表を迫る、というものだった。
度重なる迫害を受け、負の遺産を背負わせてしまった自分達の末裔(子や孫の世代?)の怨念に喚び起されたジェドは―正しいやり方ではないとしても―この子らの復讐を果たすこと、それが自分達の犯した任務(罪)に対する使命(罰)と感じる。
ジェドという、心優しくもただひたすらにハンター協会に忠義を尽くした男の最後の“使命”
―的なものが最初のノリだったが、色々な演出上の都合を足したらああなった、という感じだろうか。
とりあえず、私はそう採ってみた。
ただ、もしそうゆうノリの意味だったなら煉獄の能力は、「死」を条件にしてはいけなかったのではなかろうか。
今回の事件自体、ジェドという協会の負の遺産が起こした事件で、修羅・餓鬼・煉獄はジェドに“操作”された被害者だった的な流れをネテロが作ってあげて(ジェドもそれを狙っていて)、最後に3兄妹が完全に自由な身にはなれなくても、“隠れて生きていかずに済んだ”みたいな〆にしてあげれば、かなり違ったように思われる。
◆感想
怨の設定間違えちゃったよね、というのに尽きる。
制作陣の誰も突っ込まなかったのだろうか。
“対極になってないじゃん”
―と。
対極にもなっていないのに対比の関係を作ろうとして、わけのわからない怨の設定を重ねていくものだから、終始ふわっふわっ。
怨はラノベ?とかにありがちな“ぼくのかんがえたさいつよのうりょく”みたいなノリなのだろうが、それをどう崩すかという流れも特になく基本ゴリ押しなので“H×Hの良さ”も捨て去ってしまっている。
そして、ゴンは一体何回ジャジャン拳を放ったのか。
長期戦になるならそれなりの戦法を立て、オーラを節約させるような立ち回りや行動を描きつつ、もはやジャジャン拳を1発放てるかどうかのところで最後のあの流れに持ち込んで行ったらまた違った気もするんですけどね。
また怨なんてふわふわしたものじゃなくて、例の如く特質系能力者というサンクチュアリ使えばよかったのでは?
2作連続でボスが特質系能力者ってのが微妙なら、操作系能力者でもいい。
「影」に自らの血を媒介とする操作系あるいは特質系の能力者がおり、元々は血を固めて攻撃や防御を行ったり、血を相手に抽入することで強度の拒絶反応を起こさせるといった具合に「毒」としても使っている能力者が居たとする。
そしてその発展として“血の忠誠”があり、浴びせたり、抽入したり、血液で作った武器で攻撃した際に体内に侵入させるなどした際、相手が受け入れなければ前述の通り「毒」でしかないが、相手が受け入れれれば=術者に忠誠を誓えば―攻撃できない代わりに―血は毒から一転、強力な滋養効果を持つ薬に変わり力が強まるような効果がある。
しかし、何らの理由で術者は非業の死を遂げる。
術者が死んだことで、“血の忠誠”を誓った者達は力が弱まるどころか逆に力が強まった。
術者が緊急時様に保管していた血液を元に調べた結果、“血の忠誠”は血を媒介として死者の念として遺っていたことがわかった。
「影」達はその死者の念によって強まった“血の忠誠”を「怨」と呼び、さらに強まった力に驕り、自らを念能力者を超えた存在、「怨能力者」と称し、その勢いをさらに増していった。
(死者の念によって死者の恨みの感情をモロに受けることで、徐々に歪んで行った)
結果、「影」達はネテロに討伐されることとなり、「怨」に侵され生き残った者達は治療施設に送られるも治ることなく次第に発狂し自壊していった。
修羅・餓鬼・煉獄は、怨に縁のなかった非・戦闘部隊の者達と暮らしていたため“血の忠誠”は行っておらず、影とハンター協会の戦争も自称被害者の自分達の一族の言い分のみを聞かされていた。
何故自分達が迫害されなければいけないのか。
何故自分達が身を隠し生きて行かねばならないのか。
次第にその感情を膨らませていった。
そんな折、修羅は影の歴史や「怨」について記した手記と“血液”(カートリッジ)を発見。
修羅は“血(DNA)を元にその人物を具現”する“物真似鳥(シェイプシフター)”を発現し「影」で語り継がれる伝説のハンター・ジェドを復活させる。
(“血の粛清”は元々ジェドの能力ではなく術者の血を受けた二次母体に過ぎなかったのだが、術者の血と混ざりあって馴染んだジェド自身の血液でも“血の粛清”の効果が生まれた。ジェドが二次母体であること、また修羅・餓鬼・煉獄に分ける事になったジェドの血は、残されたジェドの血(カートリッジ)を元に修羅の能力で創られたいわば“フィクション”であることが鍵になる)
そこから「題目の意味」のところで触れたような流れに繋いでいけば、映画内の「怨」の様にチート性能を付与せずに“ゴン達でも打開できうる強力な敵”を演出できる様な気もする。
また、
怨に目覚めると“せいやく”しないと死ぬだとか
“せいやく”をジェドに交わしているような節だとか
怨に目覚めると念を使えない(血の制約を結ぶまでは強力な毒のため、心身が非常な不安定な状態に陥り念が上手く扱えない)だとか
怨に目覚めることで全系統100%はやりすぎにしても、力が強まることだとか
概ね解決できるのではなかろうか。
―とまぁ、私の大好きな妄想を繰り広げてみたが、上映中どうしたら良くなるのか、こうした方がよくないだろうか、こうすべきではなかった、こう演出した方がよかった、とやたら余計なことを考えていた気がする。
私はレイトショー?(夜8時以降の上映で1200円)で見たんですが、それでも高く感じてしまったかなぁ。
ワンコインなら別によかったかな、と思う部分もあるので自分の中で映画の点数は40点くらいなんですかねぇ。
戦闘シーンの動きの描写は…うん、頑張っていたような気がする。
と、そんな感じでしょーか!
以上。
HUNTER×HUNTER 再開決定(詳細日程発表待ち)
◆HUNTER×HUNTER 連載再開決定
公式HP(http://shonenjump.com/j/sp_hxhback/ )にて、ついにH×Hの再開が告知された。
具体的な掲載号や掲載期間は現在不明。
4/28(月)発売の22・23合併号にて、詳細の発表があるとのこと。
いつ休載したのかとブログ遡って見たら、2012年の3月19日ですと…。
そりゃこれだけ月日が経てば、結婚して子供も産まれますわなぁ……、知人に。
嬉しいけれど、色々と心中複雑なニュース。
【WJ27号(6/2)~】HUNTER×HUNTER【再開】
◆H×H 連載再開!
HUNTER×HUNTER、6/2発売の27号より連載再開!
(以前の「10週掲載」の様な限定はなし)
1ヶ月後…か。
まぁ、でも“連載が不安定”な冨樫さんをストック0の状態でGOサインは出せないだろうし、1ヶ月後の連載ということでさらに+αストックは作れそうだから、20週くらいはいくのかなぁ。
そう思えば、既に2年以上待ってるし1ヶ月なんて誤差みたいなもんか。
しかし、面白そうだなぁ。
今にも死にそうなじいさん(生命維持装置つき?)と、若かりしネテロ?がギブアンドテイクの交渉を行った模様
一転して、何かがきっかけで「災厄(アルマゲドン)」―地獄の釜のフタがあく
そして、“私の知る限りそんな夢想家(バカ)は一人しか思い浮かばないわね”…と続く。
人類が暗黒大陸に進出しようとする度、大きな災いがふりかかったという古文書やらがあったらしいので「災厄(アルマゲドン)」とは暗黒大陸のことだろうか。
ルビがアルマゲドンだから「争い」か。いや、“ハルマゲドン”自体いくつか解釈あったハズだから、世界の終末の決戦の地(メギドの丘)=暗黒大陸でも、戦争を終わらせる最後の戦争―終末戦争=暗黒大陸絡みの争いでも別におかしくはないか。
(ハンタの世界の)現状として、これまで暗黒大陸にはノータッチ体制だったみたいだから、
立場上ノータッチ派のネテロ と 進出志向の死にそうなじじい(以後、死爺)
の対話だったのだろうか。
進出やめさせることが目的で、
・ハンターライセンスもなく特段でかい犯罪歴もない様子のビヨンドの突然の表舞台登場
・ネテロが死んだ場合に備えて映像(メッセージ)を残していたこと
を思うと、死爺がネテロ(の強さ)に惚れ込んで将来的な暗黒大陸進出に備え子種を要求し、ネテロは自分の目が黒い内(生存中)は進出やめろ、が落としどころだったのだろうか。
V5からの指令だったのだろうが、蟻に対しては問答無用で“駆除”だったにも拘わらず、死爺の時には武力行使に及ばなかったことを考えれば、相当な権力者?V5的に迂闊に手を出せないような理由があるのだろうか。
死爺、“先住民系”のドンだったりして。
そして、明かされたネームの最後の流れからすると、アルマゲドン回避のために暗黒大陸進出をさせる他なく、“こっち側の人間”として死爺に同調(?)でき送り込める夢想家(バカ)は…、といった感じなのだろうか。
でもそうだとすると、死爺=夢想家になっちゃうから“先住民系”のもつ夢とはズレ込む気がするなぁ。
まぁ、5コマだけあれこれ想像しても、妄想要素が多すぎてあんま面白くもないか。
それでは再来月~(`・ω・´)ノシ
“数年振りの招かざる客”?
◆数年振りの招かざる客?
自由帳より出張。
GIが仮想世界ではなく現実世界にあると気づいた旅団は、攻略によるアイテム入手ではなく、外部から侵入した上でのアイテム略奪を企てた。
不正な方法でGIに侵入した者は強制退出させられてしまうのだった。
―さて、今回の疑問点だが、それはレイザーの言葉
“招かざる客は何年ぶりだろうな”
である。
シャルナークの推測は、
除念師を探すクロロは、ネオンの予言を元にヨークシンを東に進み、GIと知らずに旅団と同じ方法で入島を試みてレイザーに飛ばされた
というもので、
(GIに入れない)クロロの名前を敢えて使う案の出どころを除いては、ヒソカに否定されなかった。
6歳で極めた(キリ
(7歳だったかな………まぁいいや)
じゃないが、僅かでも違うことをイチイチ否定・訂正なんて面倒な事はしないわけで、概ねの内容が合っており話に齟齬が生まれなければ、そのまま話を進めるだろうから、一応現段階では
“シャルの推論は(概ね)合っている”
程度の解釈に抑えておく。
と、ここまでが再確認・情報共有。
そうして本題だが、シャルの推論が(概ね)正しいならばレイザーの発言、
“招かざる客は何年ぶりだろうな”
―はおかしいのではないか、ということ。
結論から言えば、矛盾しているとは言えない。
いくつか考え方はあるのだろうが、大きく3つ。
1:クロロを飛ばしたのがレイザーとは限らない
レイザーは“呪文での移動とか外敵対策”などの“主に放出系のシステムを担当”しているが、『外敵担当』ではない。
そもそもレイザーは「一坪の海岸線イベント」があるため、いつくるかわからない外敵担当に“専任”すること自体無理があろう。
外敵対策の「排除(エリミネイト)」のカードがGM(ゲームマスター)なら使えることからも、状況に応じ手の空いている者に外敵対応をさせているのではなかろうか。
加えて、GM同士で情報共有がしっかりしているとも描かれていない。
担当しているシステム(or役)によっては、毎日のように実際に会って話すことも出来ないだろうし、
GM専用の情報交換システムがあったとしても―、
・ゲームを揺るがす様な重大な問題がそうそう起きない(恐らく起きていない)
・ずぼらな者は小まめに確認しない
―有効に働いているとも限らない。
また、レイザーは放出系のシステムを担当しているとは言うが、システム利用情報がいちいちリアルタイムで返って来たら邪魔で仕方ないだろうから―
(ex.アカンパニー使用 → (システム情報がレイザーへ) → レイザー「おっ、誰か使ったな)
―そうゆう仕様もないだろう。
◇時系列
1:クロロ入島
2:レイザー以外のGMが外敵対応
―(情報共有がキチンとされなかった)―
3:旅団ら外部より侵入
4:レイザーが外敵対応を受ける→ “招かざる客は何年ぶりだろうな”
というのが1つ目の解釈。
否定はできないがすっきりはしない、といったところか。
2:クロロの入島が数年以上前
レイザー曰く、GIには少なくとも数年以前には侵入者がいるのだから、その1人をクロロと考えればよい、
ということ。
クロロは、仕事でメンバーを招集した時は常に最低2人は団員がいる

―が、仕事が終われば姿を消す。
そして、目標が定まれてばメンバーを招集する。
13人全員が招集されることは珍しい様で、仕事大きさ・内容に応じて変わるようだ。
作中からも見て取れるクロロの性格からすれば当たり前なのかもしれないが、目標についてある程度の調査や盗む算段がついてから、必要なメンバーを招集しているのだろう。
そして、この時クロロが外部からの侵入を試みたであろうGIだが、元々大金持ちが多額の懸賞金をかけたことで、「お宝」があることが一部のものには知られていた。
そのため、クロロも独りの際にGIに入り、仕事のための調査や算段を立て、実際に外部から侵入を試みたのがレイザーの言う以前の外敵として処理することも可能であろう。
結果的に旅団を招集しなかったことから、
・強奪自体を無理と判断
・強奪できたとしても―正規の方法で持ち出さない限り―GIの島の外では使用できないと判断
などの何らかの理由があるのだろう。
◇時系列
1:クロロ、少なくとも数年以上前にGIに侵入を試みたことがある(強奪断念)
2:クロロ、予言の下、ヨークシンから東へ向かう
3:その途中で、以前に侵入を試みて失敗した島にぶち当たる
4:・必ずしも除念師がこの島にいるとも限らない(もっと東に行ったところかもしれない)が、GIだと知っていたなら、多数の念能力者がいるGIを後回しにする理由もないだろう
5:ヒソカを使いに出し探らせる
6:旅団ら外部より侵入
7:レイザーが外敵対応を受ける→ “招かざる客は何年ぶりだろうな”
作中根拠が乏しいため、妄想寄りのイメージは強いが、否定もできない。
しかし、0巻一問一答で出されたクロロ情報より、クロロ(旅団)が私利私欲を満たすためたけの盗賊ではない可能性があるため、クロロがGIのアイテム強奪を企てること自体に若干の疑問がある。
もちろんこの疑問自体も作中根拠はまるでないのだが。
3:クロロは招かざる客=侵入者ではない
広く採れば、ゲームを経由しないで入島しようとするものは侵入者であり、招かざる客であろうが、
GM目線が考えると、若干ズレが生じて来るのかもしれない。
GMの言う招かざる客とは、「GIと知って侵入する者(GI運営を邪魔しようとする者、アイテム強奪を企てる者など)」である。
「公共交通手段から隔離され、潮流の関係で、波にまかせてるだけでは絶対に着かない島」に入ってくる時点で十中八九クロだろうが、やはり例外は存在する。
漂流者、遭難者、冒険者などの類だろう。
・近くを航海中に事故に遭い、備え付けの小型船などで一番近くにあったGI島にやって来た。
・近くで船が難破・沈没。能力者等を代表例に、一番近くの島にゴリ押しで泳いで来た。
・横断・縦断系の旅をしており、その経路に島があった
(GIは市販の地図に載っていないため冒険者の類は入島の可能性あるのかも)。
肝心のクロロの状態だが、クラピカの鎖のせいで念能力が使えないため、纏もできず微弱なオーラが垂れ流し状態なのだろう。
あの島がGIであるとも知らず、ヨークシンからただひたすらに真東に進む、いわば冒険者に近い。
レイザーからすれば、クロロが何が目的で島に入ってきているのかはわからないが、GIでは念が使えないとお話にならない(ほとんどのカードを入手できないどころか、生存自体難しい)。
一方、クロロはオーラを纏ってもいなければ、(仮に)レイザーがオーラで煽っても反応してこない(できない)ため、能力者と思われない可能性がある(仕草などから、一般人とも思われないだろうが)。
レイザーとクロロがどのような言葉を交わしたかはわからないが、そのやりとりを加味しても「こいつ(クロロ)はGIとわかって入島したわけじゃない」と判断したならば、今回のレイザーの言葉はGM目線では合っている。
◇時系列
1:クロロ、予言の下、ヨークシンから東へ向かう
2:途中、地図にない島を発見 島内に除念師がいる可能性があるので入島
3:レイザー等、誰かしらのGMに対応され島外へ
4:ヒソカを使いに出し探らせる
5:旅団ら外部より侵入
6:レイザーが外敵対応を受ける→ “招かざる客は何年ぶりだろうな”
(クロロは冒険者の類と判断され、外敵とはみなされなかった)
むしろGMがクロロを“招かざる客”と判断すること自体、逆に難しい様に思われる上、作外の情報やら妄想に頼らないため個人的には一番しっくりきている。
最後にちょっと湧いた疑問。
GIに何らかの理由で入って来た者は全て「排除(エリミネイト)」で飛ばすのだろうか。
相手が念能力者ならば問題ないと思われるが、相手が非能力者だった場合どうなのか。
基本的に「念」は対外的に易々と教えるようなモノでもないから、非能力者をエリミネイトしちゃうのはどうなのか、と思うところもあったのだ。
まぁ、どちらかと言えば保守派がそうゆう考えを持っているだけで、天空闘技場を代表例に平気で一般人に念を見せてしまう(見えないけど)のだから、別にレイザーらGMが、「非能力者にはエリミネイトしない」とも言えず、仮に非能力者はエリミネイト以外の方法で退出させられたとしても、クロロが取る方法には変わりはないため上の話では省略させてもらった。
非能力者のガチ遭難者は、船で島外へ送ってくれたりするのかも、と思ったので最初のところで、
“シャルの推論は(概ね)合っている”
程度の解釈に抑えておいた。
シャルは「クロロも飛ばされた」と考えたが実際は飛ばされていないかも、ということ。
ただクロロがエリミネイトされなかった場合、ヒソカはわざわざ正規ルートで入るのか、という疑問もある。
非能力者で、“招かざる客”判定されなかったから、
「私有地につき入島禁止、従わない場合は実力行使でお帰り願う」
で帰ってきました、ってことならヒソカはその“実力行使”目当てに行くかもしれない。
そのため、クロロも“招かざる客”判定されなかったけどエリミネイトされた、という可能性は高そうだ。
ただ一方で、この道を考えると過去の侵入者の1人がクロロ、という線もキレイに通るかも。
過去にGIアイテムの強奪を試みたことがあれば、GIのシステムやらも良く知っているから、外部侵入は“戦うこともできずに強制排除される”し、正規ルートの利点(すれ違うだけで情報得られる)も伝えられるだろう。
ある程度の案をクロロから受けていたが、ゲーム開始時に名前を自由に決められることを知ったので遊び心を出した、ということかもしれない。
クロロがヨークシンの一件後にGIに外部侵入を試み飛ばされた、というシャルの推論にヒソカの否定が入らなかったことも、ヒソカが細かいことを指摘しなかっただけかもしれないし、クロロがヒソカへの説明の中でいくつか省いただけかもしれないため、これをもっておかしい、とも言い難いだろう。
―と、そんな感じで3点出してみたが、レイザーの“招かざる客は何年ぶりだろうな”という言葉が矛盾してるとは言えないのではないだろうか。
以上。






























































































































